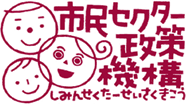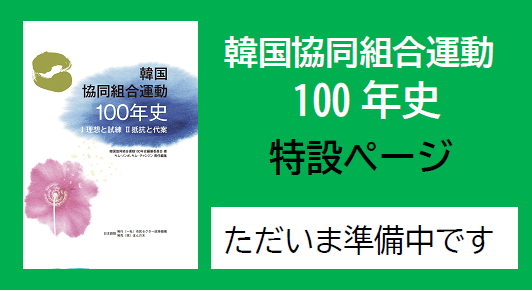6.「新しい生活様式」と視覚障がい者(全日本視覚障害者協議会総務局長 藤野喜子)
季刊『社会運動』2020年10月【440号】特集:コロナ下におけるマイノリティ -子ども、生活困窮者、障がい者、外国人-
「新しい生活様式」は、新型コロナウイルスの感染拡大を恐れて、身体的な人との接触を避けるように推奨している。しかし、小さな子ども、要介護者、障がい者は身体的接触が不可欠だ。
厚生労働省(2016年調べ)によれば、身体障害者手帳を持つ視覚障がい者は全国に31万人いる。視覚障がい者は、耳からの情報だけではなく、人や物に触ったり、杖を通じて地面を感じたり、身体的な感触を通じて生活している。
コロナ下において、視覚障がい者はどのようにして、いまの社会に向き合っているのだろうか。その一端を知るために、「全日本視覚障害者協議会」の事務所を訪ねた。
一人の人間として自由に生きたい
全日本視覚障害者協議会(以下、全視協)は、23都道府県の協議会により運営されている1967年に設立された一般社団法人で、全国に1000人の会員がいる。「視覚障害者の生活と権利を守り、差別のない平和で民主的な社会を建設すること」が目的だ。全視協の設立のきっかけは、『点字民報』という雑誌だ。視覚障がいの当事者が何に困っているのか、どのように生きていきたいかを綴っている。
自分のことは自分で決めたい。好きな仕事に就きたい。結婚したい。子どもも持ちたい。『点字民報』には、このような当事者の切実な声があふれていた。この雑誌の読者を中心に民主的な会をつくりたいという声がきっかけとなって、全視協が結成された。
取材に応じてくれた全視協の総務局長、藤野喜子さんは、5歳の時に失明し、小・中・高校と盲学校に学んだ。鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師の国家資格をもち、茅ヶ崎の地で30年、夫婦であん摩・鍼治療院を開業していた。現在は、全視協の常勤スタッフとして働いている全盲の方である。藤野さんにコロナ下での日常の変化について話を聞いた。
「私は一人で杖をついて買い物にも行きますし、電車にも乗ります。以前は、電車内で『ここに席が空いてますよ』と連れて行ってくれる人がいたり、スーパーでは『何か買いたい物はありますか』とか、町中では『駅まで一緒に行きましょう』と腕を貸す人がいました。しかし最近は、感染が心配なので人に近づいてはいけないと思い、周りにいる人も近寄らなくなりました。電車に乗っても、他の人から全く声を掛けられなくなりました。何か頼みごとがあっても、いまはお願いしづらいですね。とても買い物がしにくくなりました」
視覚障がい者にとって、「ソーシャルディスタンス」をとるように言われても、それは難しい。店のレジ前の床に引かれた間隔を示すマーカーは凹凸がなければわからない。店内で誰かに接触しないかと気を回すこともストレスだ。マスク着用について伺うと、開口一番、「マスクは困りますね」と、藤野さんの表情が曇った。
「外を歩くとき、私たち(視覚障がい者)はいろいろな感覚を使って歩いています。マスクをすると、まず匂いがしないですよね。頬に当たる風も感じなくなります。例えば、歩いていて、曲がり角に来た時に、空気が抜けていくのを感じて、方向感覚を確認したりするのです」
町で白い杖(注1)を持つ人を見かけていても、その不自由さにはなかなか想像が及ばない。視覚障がい者には、どのような障がいがあるのか。
「視覚障がいは、視力、視野、色覚の障害です。目が見えないことによる障がいは、まず行動の不自由があります。一人で歩くことは、かなり難しい。白杖を持って歩く訓練をしても、なかなか自由に歩き回ることはできません。そして情報の不自由です。本を読みたくても、点字で読める本は限られています。本が自由に読めないということは、好きな勉強が自由にできないことなのです。小説には点字の本がありますが、あらゆるジャンルであるわけではありません。いまは、パソコンの音声アプリを使って、ホームページやメールを読めるようになったので、以前とは比べものにならないくらい情報が得られますけどね」
注1 白杖は、正式名は盲人安全つえという。身体障害者福祉法の補装具に認定されている。視覚障がい者には、道路交通法で白杖の携帯が義務化されている。
(p.46-P.49 記事抜粋)