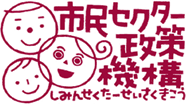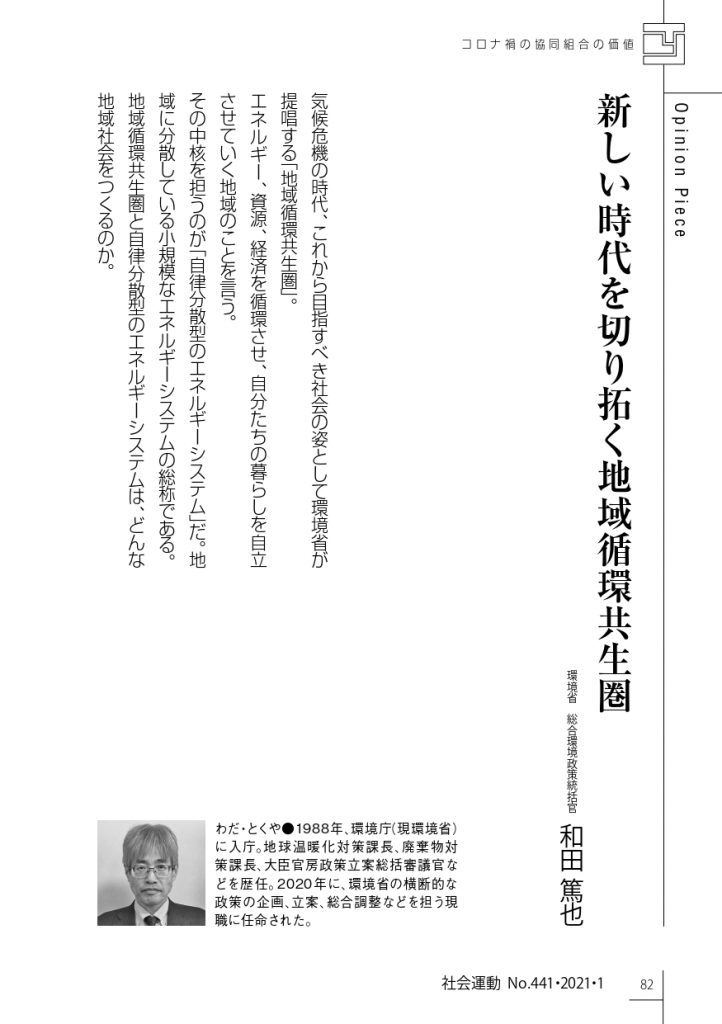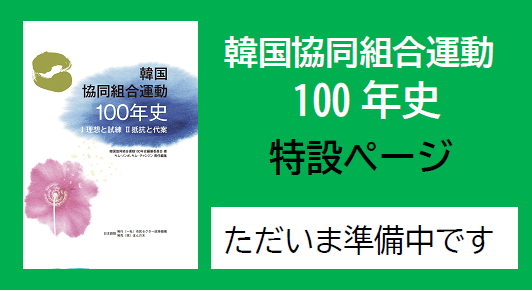7.新しい時代を切り拓く地域循環共生圏(環境省 総合環境政策統括官 和田 篤也)
もはや「防止」不可能な気候変動対策は「適応」の段階へ
世界は新型コロナウイルス感染症と気候変動という二つの危機に直面しています。いまは新型コロナに目を奪われがちですが、実は気候変動も一層、深刻化しています。これまで気候変動は長期的に取り組むべき課題とされてきましたが、現在は切迫した問題であり、緊急に対策を講じなければならない状況に追い込まれています。
北極圏では海水面積が大幅に減少し、ヨーロッパやシベリアは記録的な熱波に見舞われました。アメリカやオーストラリアでは大規模な森林火災が猛威を振るい、アフリカでは熱帯低気圧(サイクロン)が過去100年間で最悪の被害をもたらしました。日本も2018年、19年と立て続けに風水害が起こり、広い範囲に深い爪痕を残しました。
こうした巨大な災害が同時多発的に起きている原因が、地球温暖化つまり温室効果ガス排出量の増大にあることは、疑いの余地がありません。
以前は「ストップ気候変動」と言われていましたが、もはや未然に防止するのは不可能な段階に入っています。世界はこうした厳しい現実を受け止め、それに「適応」する方針へとシフトしています。温暖化した地域では栽培する農産物の見直しや品種改良を、寒冷地では熱帯地域同様の感染症対策を行うなど、各地で適応に向けた取り組みが始まっています。日本においても2018年6月に「気候変動適応法」が成立し、各分野における基本的な施策を定めた「気候変動適応計画」が策定されました。
炭素の排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」
「防止」から「適応」へといっても、温暖化を最小限に食い止める努力は続けなければなりません。その柱となるのが「カーボンニュートラル(炭素中立)」です。これは、何かを生産したり、人為的活動を行った際に、排出される二酸化炭素と吸収される二酸化炭素を同じ量にするという考え方です。すなわち、再生可能エネルギーの利用拡大や省エネ技術によって温室効果ガスを抑制するだけでなく、さらに森林や海藻による二酸化炭素の吸収によって、排出される二酸化炭素を相殺して実質ゼロにする取り組みです。こうして「プラスマイナスゼロ」すなわち「ニュートラル(中立)」にするという実態に即して、「カーボンニュートラル」と呼ばれています。
2020年10月26日に行われた内閣総理大臣の所信表明演説でも、「2050年までにカーボンニュートラルな社会の実現を目指す」と宣言されました。ここで注目すべきは、成長戦略の柱として「経済と環境の好循環」が掲げられたことです。これまではビジネスの成長を優先すれば環境対策が後回しにされるなど、経済と環境はトレードオフ(両立しない関係)にあると考えられていました。
しかしここ数年の間に、世界の価値観は大きく変わりました。日本も周回遅れながら、「経済と環境は同軸にある」というコンセンサスが形成されつつあります。霞が関でも全ての省庁が連携し、カーボンニュートラルな社会という共通の目標を目指して取り組みを推進していこうという気運が高まっています。この流れは、今後ますます加速していくでしょう。
変わる自治体の意識企業による積極的な取り組み
もう一つ注目すべき点は「脱炭素社会の実現に向けて、国と地方で検討を行う新たな場を創設する」方針が所信表明演説で示されたことです。これは国が政策を決めて、自治体はそれに従うというこれまでの基本的な行政の流れが、大きく変わることを意味しています。
この方針には、国が前面に出過ぎてしまった反省が込められています。国によるトップダウン方式ではどうしても強権的になり、達成できなかった場合の罰則をどうするかといった議論に偏りがちでした。
そこで主体を自治体、ひいては地域に暮らす一人ひとりの市民に委ね、国は政策面からバックアップしていく形に転換しようというわけです。2019年9月に、「2050年までにカーボンニュートラルを宣言する自治体」を募ったところ、現在までに170(全自治体の約10%・人口規模で約800万人)を超える市町村が名乗りを上げてくれました。自治体の意識も含めて、状況は着実に変わっていることを実感しています。
産業界でも、多くの企業が気候変動対策を経営方針の柱に位置づけ、積極的に取り組むようになりました。中には原材料の調達から輸送、製造、廃棄に至るサプライチェーン全体で、使用エネルギーの全てを再生可能エネルギーに転換するという野心的な目標を掲げた企業もあります。
以前はビジネスと環境は相反するものと考えられていましたが、現在は環境への取り組みが事業継続や企業価値の向上につながるという認識が一般化しています。こうした変化の根底には、企業にとって気候変動は大きなリスクになるという切実な問題があります。一度災害が発生すれば従業員の被害、サプライチェーンの断絶、原材料の調達コスト増大など、様々な形でビジネスに深刻な影響をもたらします。こうしたリスクを最小限にするためにも、対策は必須なのです。
さらに一歩進んで、気候変動対策をビジネスチャンスにつなげる潮流も生まれています。一例として、各ハウスメーカーが開発に取り組んでいるのが「ゼロエネルギーハウス(ZEH)」です。この家は、太陽光発電や燃料電池によってエネルギーを作ることで、年間のエネルギー消費量がプラスマイナスゼロになるのです。環境性に優れているだけでなく、災害時にエネルギーが確保でき、さらに高い断熱性による快適な住環境など、これまでの家にはない付加価値を生み出しています。ハウスメーカーもZEHへの置き換えを推進することで、自社ビジネスの持続可能な成長も実現させたいと考えています。
環境省が提唱する「地域循環共生圏」
環境省が、これから目指すべき社会の姿として提唱しているのが「地域循環共生圏」です。以下のように言葉を分割すると、そのコンセプトがわかりやすいと思います。
・「地域」とは、地方自治体の活力を最大限に発揮することです。
・「循環」とは、エネルギー、資源、経済を循環させることです。
・「共生」とは、人と自然、人と人、地域どうしの共生を広げることです。
・「圏」には、各地域の自立(オーナーシップ)という意味が込められています。つまりそこに暮らす人びとが自分の地域に誇りと愛着を持ち、主体的に取り組みに参加するというシナリオです。
こうして自立を自分たちの課題と考えた地域が、ネットワークを形成して支え合う。それが地域循環共生圏の目指す姿です。例えば、農山漁村は豊かな自然の恵みを生かした農産物やエネルギーを都市に提供し、都市はエコツーリズムや自然保護活動への参加によって農山漁村を潤わせる。こうして互いの資源を融通し合うことで経済、環境、社会に好循環が生まれ、持続可能な地域の成長につながるのです(図1)。
「地域循環共生圏」の中核にある分散型エネルギーシステム
地域循環共生圏は、次の五つの柱で成り立っています。
①自律分散型のエネルギーシステム
②災害に強いまちづくり
③人に優しく魅力ある交通・移動システム
④健康で自然とのつながりを感じるライフスタイル
⑤地域における多様なビジネスの創出
その中核を担うのが「自律分散型のエネルギーシステム」です。これは、各地域に分散している比較的小規模なエネルギーシステムの総称です。具体的には太陽光・太陽熱、小水力、木質バイオマスといった再生可能エルギー、地中熱や河川熱といった未利用エネルギー、電気と熱を同時に作り出すコージェネレーション、水素で発電する燃料電池など多種多様な種類があります。
これまでのエネルギーは海外から化石資源を輸入し、大規模集中型の発電所で作られた電力を利用するのが一般的でした。これに対して分散型エネルギーシステムは、エネルギーを使う地域で資源を調達し、自前のプラントで電気や熱を作る「地産地消」を推進することで、地域の新たな成長を促します。
こうして再生可能エネルギーの利用が拡大すれば「カーボンニュートラル」が実現します。システムを統合した電力システムから独立させることで、停電時の電力供給も可能になり「災害に強いまちづくり」にも貢献します。さらにはエネルギーを軸にした「多様なビジネスの創出」によって地域経済の活性化につながるなど、多くの相乗効果が期待できます。
原発などこれまでのエネルギー施設は「迷惑施設」として誘致が敬遠されがちでしたが、地域が主体的に取り組む分散型エネルギーシステムであれば、全く違う展開が見えてくるはずです。
生活者のニーズに基づき地域社会を構想する時代
これらの活動に共通しているのは、「暮らしと生活者の目線から考えよう」ということです。少し前まで、行政の考えは生活者目線ではなく、供給サイド、つまり産業界のコンセプトが強く、補助金を使って地方自治体を従わせていました。これは明治開闢以来の霞が関行政の問題点の一つだと、私は思っています。
(p.83-P.88 記事抜粋)