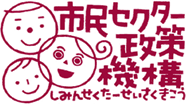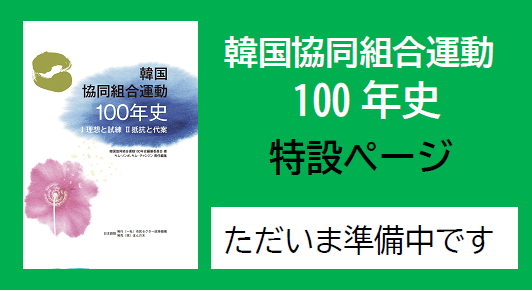2.母子家庭の貧困 その根底にある母親の労働条件を考える(労働経済ジャーナリスト 小林美希)
「女性」「妊娠・出産」「育児」で賃金ペナルティが課せられる
日本の一人親世帯数は約142万世帯。うち母子家庭の数は約123万世帯で、9割近くを占めている。2016年度に行われた厚生労働省の調査(注)によるものだが、詳しく見ると以下のようになる。
母子世帯と父子世帯の就業状況はともに8割以上だが、母子世帯の4割以上がパート・アルバイトであるのに対し、父子世帯のそれは1割以下。平均年収(就労収入)は、母子世帯が200万円で、父子世帯は398万円。
共働き夫婦が増えているいま、一人親世帯の収入は相対的に低く、いずれも全世帯平均の545万円を下回っているが、母子世帯のほうがより深刻な状況に置かれていることがわかる。200万円は平均値なので、多くの母子世帯の収入はこれ以下ということだ。
こうした男女の就労・経済的格差は、一人親になる前、妊娠・出産の時点から始まっている。小林さんは女性の就労について、「大学卒業時の就職率を見ると男女差はほとんどなく、就職氷河期世代(1993〜2005年ごろに就職)といわれたいまの子育て世代で見ても、女性のほうがやや高いほど。しかし働き始めると、多くの女性は差別に直面します。年齢を重ねるほど、男性との賃金・待遇の格差は大きくなる」と解説する。
さらに、「男は仕事、女は家庭」という古い価値観を背景にしたマタニティ・ハラスメント(以下、マタハラ)が横行。働く母親へ向けられる世間の目は、大手の企業であっても、いまだ厳しい。産休・育休のあと、職場復帰をしても保育所の送り迎えなどで時短勤務となり、キャリアダウンするのは父親ではなく母親のほうだ。
「キャリアダウンなら、まだいい方。『寿退社』が、『妊娠解雇』に置き換わっているのが現状です。妊娠を理由に解雇することは法律で禁じられていますが、無理な業務を強いて自主退社に追い込むなど、やり方はいくらでもある。国立社会保障・人口問題研究所の出生動向調査によると、第1子出産を機に約5〜6割の女性が無職になっており、ここ30年ほど変わっていません」
このことを裏付けている、日本労働組合総連合会(以下、連合)が行った「働く女性の妊娠に関する調査(2015年2月発表)」がある。「妊娠後に、その当時の仕事を続けたか、辞めたか」という問いに対して、正社員・正職員でも51・9%が「辞めた」と答え、契約社員では69・7%、パート・アルバイトでは73・6%もの割合で「辞めた」と答えている(23ページグラフ参照)。
そのうち、約半数が「家事育児に専念するため自主的に」を理由にしているが、「仕事を続けたかったが、仕事と育児の両立の難しさから」が21・1%、「仕事を続けたかったが、妊娠を機に、解雇やパートへの身分の変更を求められるなど、不利益な取り扱いを受けたから」が7・2%だった(複数回答)。
否応なく離職する女性は決して少なくない。また、妊娠で解雇される女性の多くが、非正規雇用であり、そもそも女性の正規雇用を減らしている企業も増えている。
「新卒は正規で採用しても、転職や中途採用の場合は非正規雇用や派遣にして、契約期間を数カ月ごと、1年ごとと細切れにする。そうやって、合法的にクビを切りやすい状態にしておくわけです。さらに、業務請負契約や個人事業主として契約している女性は、社会保険や育児休暇も望めません。公務員の世界も同じく、非正規の職員は全体として増えていて、そこに女性が押し込められやすい構造になっています」
(P.20~P.22記事抜粋)