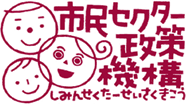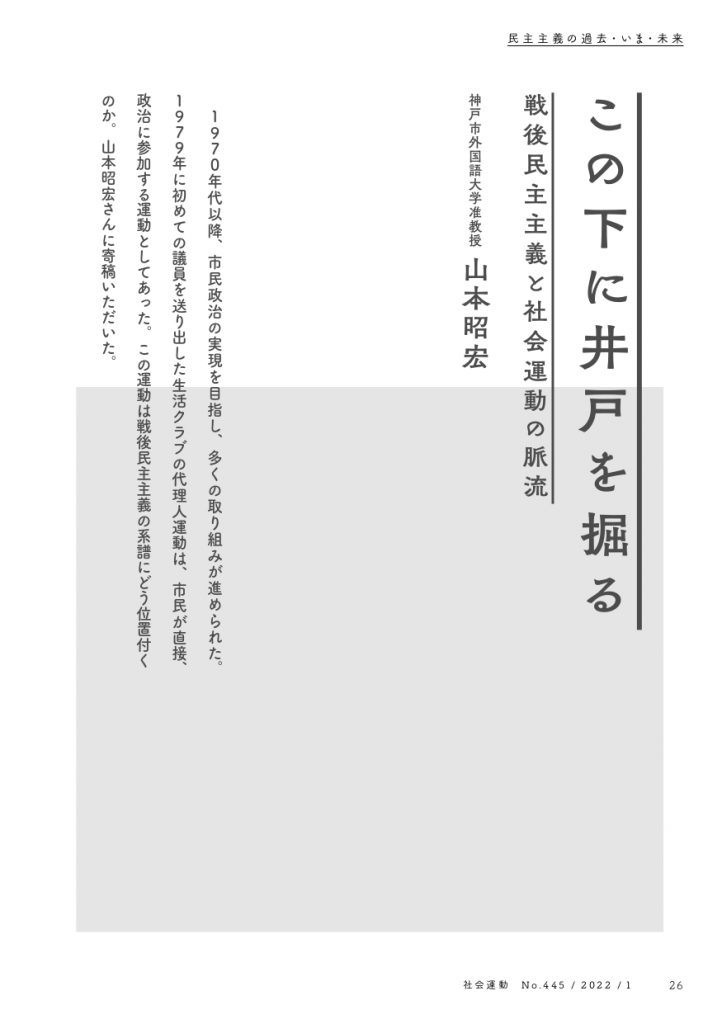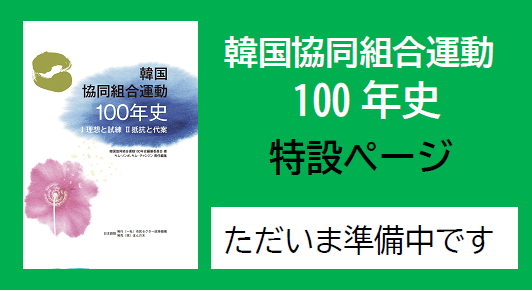③この下に井戸を掘る(神戸市外国語大学准教授 山本昭宏)
「運動」への距離感 二つの要素
社会学者で生活者論が専門の天野正子は、代理人運動を「間接民主制に直接民主制の要素をとりこみ、市民自治の確立をめざそうとする一つの壮大な実験」だったと評価した(天野正子『「生活者」とはだれか』中央公論社1996)。天野の指摘をさらに展開するならば、生活クラブ生協による代理人運動は、「代表とはなにか」「政治のプロとは誰か」という根本的な問いかけを含んでおり、その問いかけは今なお色あせていない。生活者の戦後史のなかでも見逃すことのできない重要な運動だったと言っていい。
しかしながら、現代の日本社会では「市民自治の確立」に関わる諸運動が見えにくくなっている。その理由はどこにあるのか。現代日本社会には、次の二つの「落とし穴」があると思われる。
第一に、「運動」という要素の囲い出しである。
現代の私たちは、「より良い生」をプライベートに限定して理解しがちだ。例を挙げると、家族の構成員の人格や属性(年齢・性別・職業)のなかにも他者性があり、その意味では家族にも公共性があると言えるが、家族は私的領域だと信じて疑わず、ドアの外を想像することは少ないのではないか。友人関係にしても同じである。日常生活にそくして言えば、プライベートと地域社会を完全に切り分け、前者に後者が入り込むことを怖がっているようにみえる。それと関係して進むのが、私的領域の豊かさを経済的利益と直結させる自閉性である。自閉性は、経済的利益を少しでも増やすことのできる条件を素早く整えてほしいという願望となる。願望は、それが可能だと思える政党に政治を任せ切ってしまうという態度に向かう。そこに社会運動が入り込む余地はない―そのような考えが自明視されてはいないだろうか。要は、「運動」という言葉を切り縮めて、自分たちに関わりのないものとして囲い出してしまっているということだ。豊かさの尺度が経済に一元化されていると言い換えてもよい。家族や友人や職場というコミュニティに参加し、それを通して心地よい環境を作るという広義の「運動」の近くにいながら、それを認識できていないのだ。
第二に、社会批判の否認である。
批判という精神の動きは、対象を分析的に捉えて問題点を把握するものだが、現代の日常では批判という言葉はほぼ「否定」と同じ意味で使われることが多く、それゆえネガティブかつ攻撃的で、集団の和を乱すものとして捉えられがちだ。「友人と政治の話をしづらい」という感想を耳にすることがあるが、それもここから生じたものだろう。社会批判の否認は、保守層のみならず、「現状のこのやり方でやるしかないのだ」という切迫感として若年層をも取り囲んでいるように思える。こうした態度は実は諦観と表裏一体で、第一の要素と手を取り合って、現代社会の基調をなしつつあるように見える。
以上の二点は、ながらく現代の私たちを縛っているが、「なにかオカシイ」「黙っていられない」という思いが社会から消えたわけではない。二つの「落とし穴」を軽やかに、そして粘り強く回避している運動は、現代にも多様に存在している。それは、「なにかオカシイ」「任せておけない」と感じた人びとが、政治に任せ切ってしまうのではなく、できるところから、できる範囲で「この下に井戸を掘る」という活動だ。自分の問題や自分たちの課題への継続的な取り組みは、実は他者とその問題に通じる横穴を掘る作業でもある。そして、そこにこそ連帯の可能性がある。
繰り返すが、生活の至るところに民主主義があるという主権者意識が、戦後民主主義の根幹にある。もし、戦後民主主義という言葉が嫌ならば、別にこの言葉にこだわる必要はない。言葉よりも、戦後社会が培ってきた精神性こそが重要で、それを現代的に磨き直す作業は、その気になれば今すぐにでも始められるはずだ。自分にとって「より良い生活」とは何か―それを測る尺度を複数用意するために、まずは窓を開けて光を取り込みたい。
(p.32-P.35 記事抜粋)