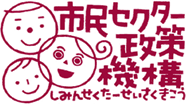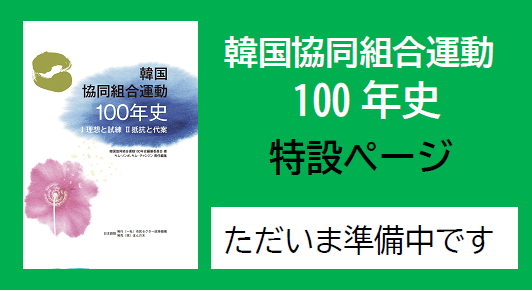北海道ルポルタージュ①
「先が見えない」畜産農家の苦悩〜食料危機の最前線から
((有)肉牛工房ゆうあいファーム 代表取締役 伊藤浩市)
大事なのは牛を毎日「見る」こと
目、顔つき、動きで健康状態が分かる
(有)肉牛工房ゆうあいファームは、オホーツク海とサロマ湖に面した道東の湧別町東地区にある牧場だ。ここで飼養されているのは、生後1週間~19カ月齢までの乳用種去勢牛(去勢したホルスタインのオス)約1000頭。100パーセント地元で生産した良質の牧草や干し草を与え、健康的な国産牛を生産しているほか、別法人で酪農事業も行っている。
「毎月、素牛(生後7カ月前後)が平均で20頭、子牛(生後1週間~1カ月以内)が40頭、計60頭入ってきて、素牛は約13カ月、子牛は約19カ月育てて出荷します。スタッフは僕を含め4人ですが、僕は事務や外部の仕事もあるので0・5人分。実質3・5人で回している感じですね。いちばん若いスタッフで30代半ば、上は50代なので新しい若手が欲しいのですが、難しいです。どこも人手不足で。僕も63歳。そろそろ第二の人生を考えたいんですけど」と話す、代表取締役の伊藤浩市さん。
そう言いながらも「この仕事は生涯やっていけるからね」と笑う。根っからの牛飼いなのだ。起床は毎朝4時。伊藤さんの朝は、牛を一頭一頭「見る」ことから始まる。
「まずは、搾乳牛舎。エサやりは基本的にはロボットがやるんですが、うまくエサを食べられない牛もいるので、ちゃんと見て確認する必要があるんです。全部で200頭くらいかな。それを2時間くらいでやって、次は肉牛の健康状態を1頭ずつ見て回り、朝8時からのミーティングでスタッフに共有します。やはり長年、牛を見ている人でないと、牛の目や顔つき、動きの微妙な変化や、ただ寝ているのか調子が悪くて寝ているのかといった判断は難しいです。獣医さんも『毎日見ている人にはかなわない』と言いますよ。特に大事なのは、4カ月くらいまでの子牛。ここで体を壊しちゃうと後々まで尾を引くので、風邪を引かせないよう、下痢させないよう気をつけます。調子が悪い牛がいたら、必要に応じて獣医さんを呼び、薬を処方してもらう。治療を続けるか、見切りをつけるか判断するのも僕の役目です。スタッフにやらせるのは酷ですから。このまま薬代をかけて治療しても良くならないだろうとか、いくらいいエサをやってもサイズが基準値に届かないと判断したら、淘汰(処分)に回す。こればっかりは経済動物なので、仕方ないです」
牛の見回りが終わると、あとは通常の業務(エサの調整、掃除、獣医師への対応、機械や施設のメンテナンスなど)や、外回りの仕事、事務仕事。これに月に5、6回は子牛や素牛の導入、出荷作業も加わる。夕方のミーティングを終えたらスタッフは解散となるが、伊藤さんの仕事に終わりはない。
「搾乳などのロボットにエラーが出ると、24時間いつでも携帯電話に連絡が入るようになっています。特に、気温が零下20℃以下になることもある冬は、機械が凍ったりして動かなくなるトラブルが起こりやすい。ひと仕事終えて一杯やろうかなってときや、真夜中に呼び出されると、まいっちゃいますね。まるでこっちがロボットに管理されているみたいです」
2000年代のBSE、農協の合併で
地域の8割以上が離農した
1950年代に酪農で入植したという先代(伊藤さんの実父)は、伊藤さんが中学校に入る70年代半ばごろ、肉牛の生産に着手したという。
「いまは雌雄選別という技術で、オス・メスの産み分けが可能になっていますが、昔はオス・メスが半々で生まれてくるでしょう。酪農では乳を出さないオスは不要ですから、ほとんど捨てられていたような時代。それを去勢してエサを与え肉牛にする方法を父がどこからか習ってきたんです。
とはいえ当時は専用のエサなんてないし、効果的に太らせる方法もよくわからなくて、市場に持っていっても『こんなのは肉牛じゃない』と買い叩かれ、大赤字だったそうです。それでも牛肉の需要が増えるに連れて肉牛生産を始める人が増え、エサ屋さんも肉牛用のエサを作るようになって、ホルスタインのオスが付加価値の付いた商品として売れるようになりました。うちも、僕が高校を出るころには肉牛事業がメインになっていましたね。
一方、母は、廃鶏(卵を産まなくなった鶏)を食肉に加工する仕事を営んでいました。昔は畑作農家が、鶏糞を肥料にするために、あるいは農閑期の副業として卵を売るために、鶏を飼うことが多かったので、あちこちで廃鶏が出るんです。それを集めて加工するという仕事があったんですね。僕もよく首切りを手伝いました。いまでも鶏肉を見ると、どこか懐かしいような気持ちになります」
伊藤さんが家業を継いだのは、30代半ばの1995年ごろで、当時の飼養頭数は500頭ほど。徐々に規模を拡大し、2001年ごろには1500頭ほどの肉牛を育てるまでになった。ただ、経営は継いだ当初からずっと厳しかったという。
「継いだときは、借金が3000万円くらいあったかな。父の代では、オイルショックや牛肉・乳製品の輸入自由化のあおりを受けましたが、僕の代になって大きかったのは、牛海綿状脳症(BSE)ですね(※2001年に国内でもBSEが発見され牛肉の価格が暴落した)。2002年には、この地域に3つあった農協が合併し、経営状態の悪い農家は受け入れてもらえず、仲間の8~9割が離農しました。うちは持ちこたえましたが、2003年から肉牛はすべて北海道チクレン農業協同組合連合会(以下、北海道チクレン)の作業委託に切り替えました。近隣の牧場も、いまではほとんどが作業委託です」
(P.31ーP.33 記事抜粋)