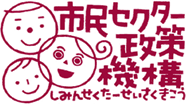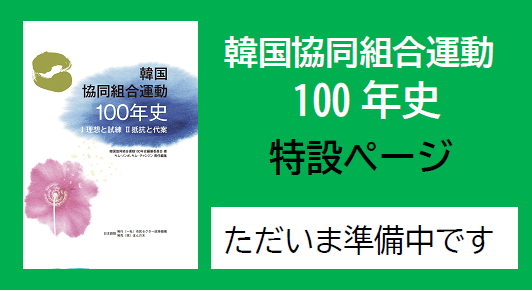③使用価値を決める関係を重視する「半市場経済」の構想(哲学者 内山 節)
使用価値と交換価値
商品の価値には「使用価値」と「交換価値」とがあると、経済学の基礎をつくったアダム・スミスは指摘しました。使用価値というのは、使った時の有用性のことですから、使用価値がたくさんあるような経済社会では、みんなが豊かになっていくわけです。それに対して、私たちが普段なじんでいる市場経済は、値段で表される交換価値で成り立っています。
アダム・スミスは、いまから250年近く前の『国富論』のなかで、「ダイヤモンドには非常に大きな交換価値があるが、何の使用価値もない」と言っています。それに対して「水は非常に大きな使用価値をもっていて、場合によってはコップ1杯の水がないために、死んでしまう場合もある。それだけの使用価値があるのに、水には何の交換価値もない」と言います。これが有名な「水とダイヤモンドの例え」なのですが、ダイヤモンドに使用価値があるかないかについての議論は別にしても、使用価値と交換価値というのが、必ずしも比例してはいない、ということは感覚的に理解できるのではないでしょうか。
しかし、使用価値を経済学の基礎に置こうとすると、水は時として人間の命を救うほど重要な使用価値を持つものの、それが状況によって変わってしまうということが問題となります。砂漠で水を求めてさまよっている人にコップ1杯の水を提供すれば、命を助けるような大きな使用価値を持っている。でも湿潤で水の豊富な地域で、しかも水をたくさん飲んできたばかりの人に、コップ1杯の水を出されても、正直、「いらない」という気分になるでしょう。ここでは使用価値はほとんどない。
あるいは老夫婦が、孫から自分たちを描いた下手な絵を誕生日にプレゼントされたとします。他の人から見たら、ただの下手な絵であっても、老夫婦にとっては名画にも値する価値があると感じるということはありえるわけですね。
このように使用価値というのは伸び縮みしてしまい、量を確定することができないのです。一方で交換価値の方は、市場で交換する時の価値ですから、要するに値札に示された金額で確定できるわけです。
アダム・スミスは経済発展を通して人びとを豊かにするという目的意識がありましたので、使用価値の経済学を作りたいという思いがあったのでした。しかし、使用価値量を確定できなかったので、その後の経済展開を論理的に説明することができず、諦めてしまいました。結局、経済学というのは交換価値だけを対象にせざるをえなくなります。そうなると、市場に流通する商品を1兆円から2兆円に増やせば、経済規模は倍になり、それに伴って「人びとも豊かになったのだ」と経済学者は言い張るようになるわけです。しかしながら、交換価値による市場規模が大きくなっても、人びとが豊かさを感じられない、むしろ格差社会が酷くなったなどということは往々にして起きてしまいます。
あるいは100円ショップに行くと、100円で買えるものを「よくもこれだけ揃えたものだ」と感心するくらい様々なものがあります。しかし私からみれば「これを作った人たちは大変だったろうな、納入している業者はいったいいくらで納入したのだろう、そこで働く人たちには果たしてまともな賃金が払われているのだろうか」といったことに気が向いてしまいます。そういう視点で見ていくと、交換価値、つまり値段というものは人びとが求める価値を表してはいないということがはっきり見えてきます。
このように経済学というのは、純粋に理論を追い求めると、人びとを豊かにするという目的をうまく実現できない、そういうジレンマを出だしから抱えていたのです。そういう忸怩たる思いを、現代経済学は、ある意味忘れてしまったように思います。
(P.41-P.43 記事抜粋)