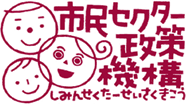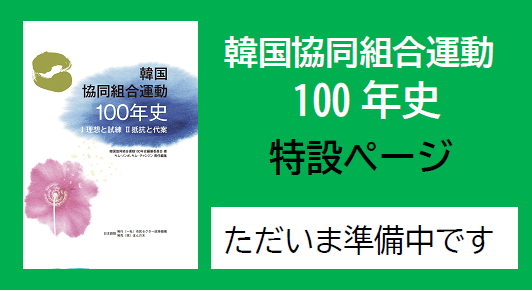書評①『くらしのアナキズム』(松村圭一郎 著 ミシマ社 2021年)
世界各地の小さき人々の暮らしのアナキー性を紹介
明治学院大学名誉教授 市民セクター政策機構理事 勝俣 誠
経済学者。西アフリカ滞在時の日々の発見と考察は『社会運動』に24回にわたり「ダカール便り」として連載。『アフリカは本当に貧しいのか』(朝日選書1993)にまとめられた。
本書の書評を依頼されたとき、マクロ目線でパワーとマネーが人類に及ぼす弊害を考える政治経済学系の自分は、アナキズムや国家論を体系だって追ったことがないために一瞬戸惑った。
ただ読み進めるうちにかつて1980年代初め、西アフリカのセネガルの首都ダカールの大学に所属することとなり、2年弱だが日々発見したミクロ世界の暮らしの中で生まれたいくつもの疑問の束と重なることが多いことに気づいた。
法経学部の教授会で隣り合わせになったフランスからの同僚(刑法)は、私が初めてサハラ以南のアフリカ生活をすることを知って、土地の生活習慣や注意すべきことをいろいろ「助言」してくれた。例えば、このクニには個人が存在せず、家族と知人の間にいることが一番の幸せであるとか、食事の招待は招待される側の方が招待者より上位に立つので、昼食時間帯に前触れなく家を訪問することさえ、礼に欠くどころか、共食の貸しを受け入れ家族に徳を積むことであるといった具合である。
実際、アフリカ人家族に泊まりに行けば、寝ていても子どもたちは枕もとを駆け巡り、突然の昼食時の家族訪問は、恐れ入るほど歓迎された。もっとも濫用は避けるべきで、いつも訪ねた学部同僚の家族からはあらかじめ一報くれると準備の関係で助かるとも言われたが。そんなダカール生活で私にとって大きな発見の一つは、あげる・もらうの関係だった。当時学部同僚の間で話題になったフランス語女性作家による『乞食のストライキ』(原題は “Greve des battus” で battusは土地の言葉でお布施をもらうため手にするひょうたん製の容器を持つ者という意。副題は“les dechets humains”「人間のゴミたち」)という短編小説があった。
この国の都市を訪れる外国人観光客が物乞いする乞食集団に悩まされている事態を解決すべく、上昇志向のキャリア官僚が乞食をバスで人目のつかない郊外に移動させてしまうストーリーだ。この処置で、乞食なき市内は乞食にまとわりつかれるうっとうしさがなくなり、観光客の評判は高まる。自信を強めたこの公務員は、さらなる昇進への道を探るためにイスラームの導師を訪れる。
導師は羊一頭を貧者に施す善行を積めば、更なる昇進が実現すると言い渡す。これで早速、羊を丸焼きして準備するのだが、肝心の施しの対象の乞食がもはや市内にいない。そこで彼は以前移動させた郊外の乞食部落に羊を施すのでもらってほしいと頼むが、前回のことを忘れない乞食団のリーダーは受け取りを拒否する。結局、この役人は、バスをチャーターして再び市内に乞食に戻ってもらうという結末だ。ここではあげるほうが偉いのか、もらうほうが偉いのかがわからくなる。換言すれば、富める者の徳とはひたすら貧者の存在によってしか実現しないのかという問いに私はぶつかった。
本書は各章が著者の出会った世界各地の小さき人々の暮らしのアナキー性を人類学業界の語彙だけでなく、政治学、社会学、社会思想史、哲学、歴史学、といった人類学の隣接科学のキーワードをも参照しながら、展開されている。
第1章は国家無くして人類は立派に生きてきたという人類学の知見からの問いかけで、第2章の権力論では、人々は臣民やネーション・ステートの国民になりきらないアナキー人のちゃっかり型暮らしが提示される。
第3章は国家なき社会での政治とは何かが問われる。そこでの政治リーダーの正統性はひたすら当人がどこまで人肌脱げるかという利他性に存し、しかも絶えずその規範から人々による民主主義的チェックにさらされる存在である。第4章はいわゆる労働や資本や不動産といった資本主義体制下の「しじょう」と「いちば」とも呼ぶべき顔の見える市場の区別を、フランスの地中海史のブローデルや中世史の網野善彦などの歴史学を参照して、いちば空間の持つ雑多に満ち満ちた異界性やアナキー性の楽しさが紹介される。
第5章ではアナキスト的民主主義の実践形態がグレーバーの政治論などに依拠して、国家目線の「政策」に翻弄されない政治なるコトが、日本のムラの反原発運動やイタリアの地域精神保健改革などの事例によって紹介される。最後の第6章は暮らしの原理は、賃金や資本の生産性にからめとられない多様な各人が共に楽しく生きられるコンヴィヴィアリティ(自立共生社会)の可能性が提示される。読み手はその問いの重さと本書の展開の軽快さに戸惑うかもしれない。各章ごとに考え込んでしまう私をほっとさせてくれたのは、著者が人類学のフィールドとしているエチオピアの村や、職場の岡山の農村史や2016年大地震に見舞われた故郷の熊本の界隈での人的交流について書いたコラム欄だ。これらの文章が重たい問いとのつながりを可視化してくれた。
(P.117-P.119記事抜粋)