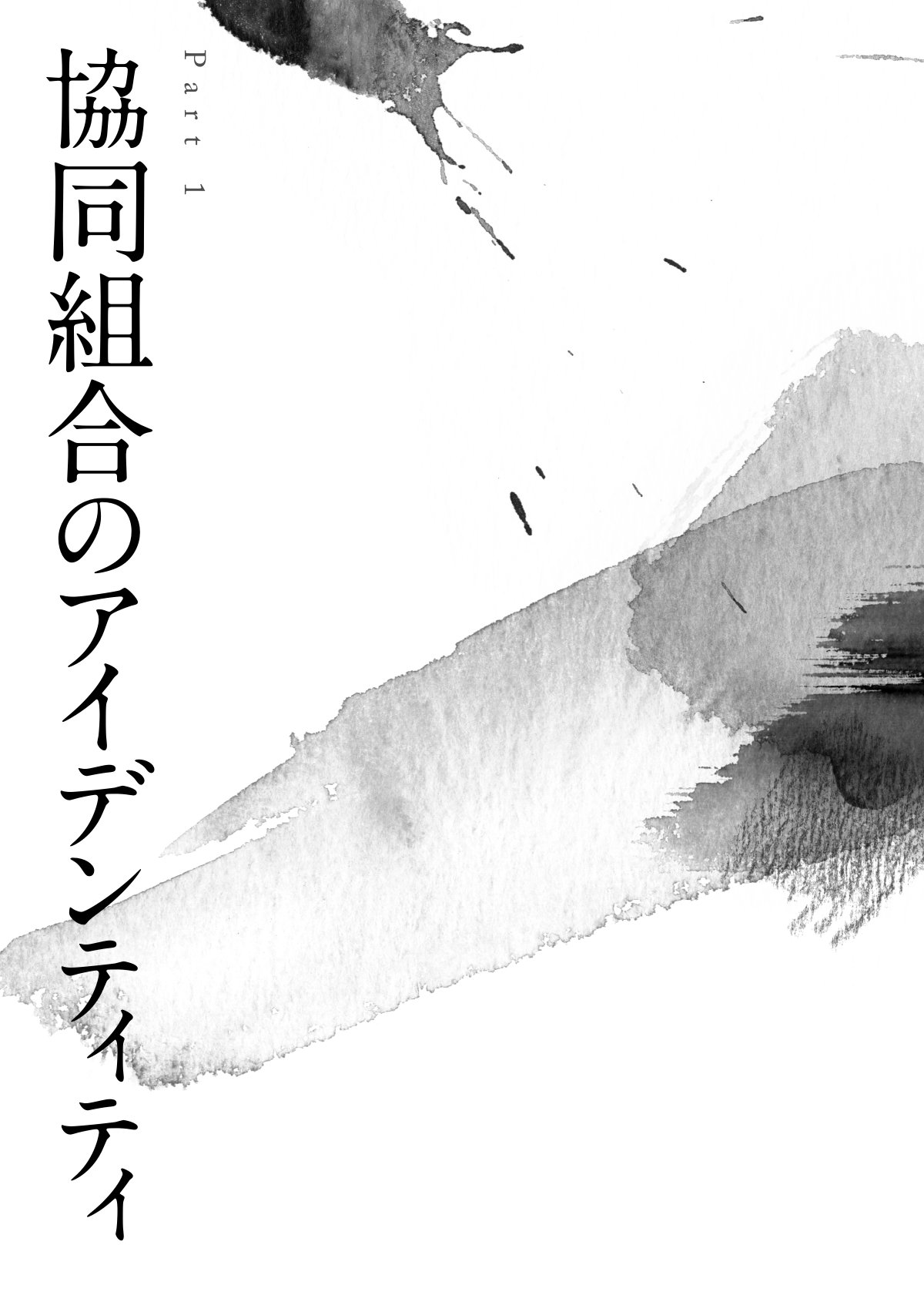いまこそ、協同組合の出番~参加・主権・責任
柳下信宏(季刊『社会運動』編集長)
国連は、SDGsの達成などに向けて協同組合が果たす役割を評価し、2025年を国際協同組合年に定め、各国政府に対して協同組合の振興を求めている。国際労働機関(ILO)も2022年総会の「ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)と社会的連帯経済に関する決議」で協同組合を評価している。日本ではなかなか実感しにくいことだが、協同組合の可能性について、国際的な期待が高まっている。
協同組合が大切にする「価値」とは
では、期待されている協同組合とは、そもそも何なのか。
本号の伊藤論文(10ページ)で述べられているように、協同組合のアイデンティティ(定義、価値、原則)に関する国際的な討議が進行中だ。協同組合とはどのような組織なのか(定義)、協同組合が大切にするものは何か(価値)、その価値を実現するためにはどのような実践が必要なのか(原則)についての議論だ。
その議論の過程において、各国の協同組合関係者にアンケート調査を行ったところ、「原則」(例えば一人一票の原則など)に関する認知度は高いものの、大切にする「価値」について認知度が低い結果となった。現行の「価値」は、「協同組合は、自助、自己責任、民主主義、平等、公正、連帯という価値を基礎とする。協同組合の創設者たちの伝統を受け継ぎ、協同組合の組合員は、正直、公開、社会的責任、他人への配慮という倫理的価値を信条とする」と定められている。
「自助、自己責任」から「相互自助、個人の責任」へ
現行の「価値」に対する改定案では、「自助」(self-help)を「相互自助」(mutual-self-help)に、「自己責任」(self-responsibility)を「個人の責任」(personal responsibility)に変更している。
自己責任という言葉は、新自由主義における自己責任論を想起させる。直接的に強制される「責任」はもとより、自己決定を装いつつ、社会的な背景を捨象し、選択の結果を「自己責任」として強いることもある。「相互自助」と「個人の責任」という表現は、個人化と自立だけを前提としない、協同の可能性を追求した討議の結果なのかもしれない。
責任とは何か
本号白井論文(38ページ)では、協同組合原則に「組合員参加」はあるが、「組合員主権」がないのはなぜかと問う。顧客としてのお飾りの参加ではなく、組合員が組織に対する決定権を持ち、主権を行使することこそが重要なのだが、この主権の行使には、「責任」が伴う。
では、この「責任」とは、選択を強制された結果の「自己責任」なのだろうか。本号で、祐成氏、税所氏が述べる居住支援や生活支援の事例(109ページ)や、藤井氏、篠崎氏、瀬戸氏の鼎談(98ページ)で語られる業務委託ワーカーズ・コレクティブの取り組みの事例では、お飾りの参加や見せかけの自己決定を超えて、主権を行使し、自らが「責任」を引き受けることで社会を変える取り組みが語られている。「やりがい搾取」という言葉もあるが、読者の皆さんは本号の事例をどう考えるだろうか。
参加と責任の増大が問題を解決する
昔話で恐縮だが、生活クラブ・神奈川の創始者である故横田克巳氏は、「参加と責任の増大が問題を解決する」とよく語っていた。責任とは否定的な文脈で語られることが多いが、ある状況中で引き受けた責任は、自らをエンパワーメントし、社会を変える力を持つことでもある。
参加・主権・責任をキーワードに本号をお読みいただけると幸いです。
(P.4-P.6 記事全文)