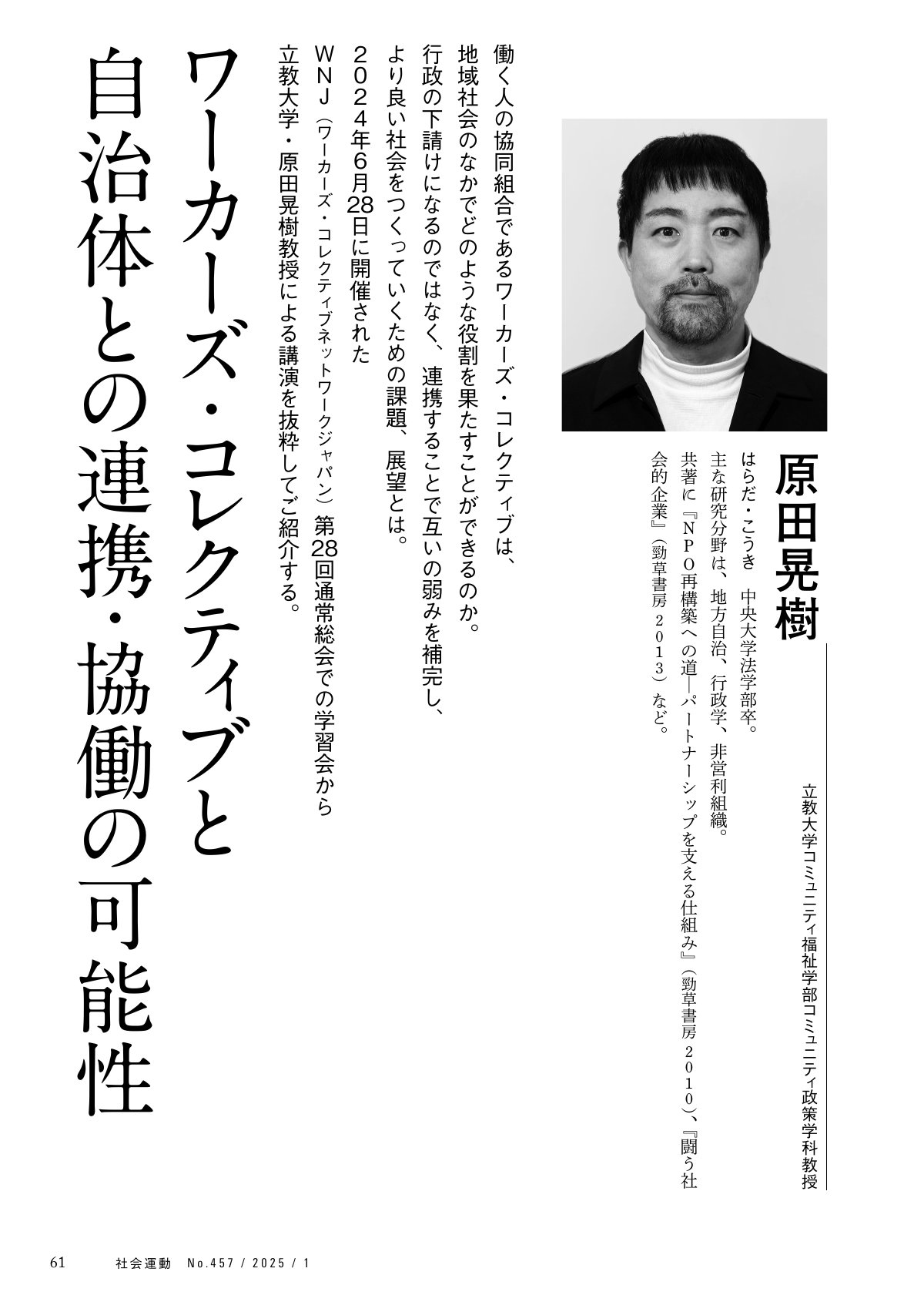②ワーカーズ・コレクティブと自治体との連携・協働の可能性
原田晃樹 (立教大学コミュニティ福祉学部教授)
私は地方自治が専門で、神奈川県では鎌倉市、川崎市などいくつかの自治体にかかわっています。そこで改めて感じたのは、自治体の非営利組織に関する対応が海外に比べて、かなり遅れているだけでなく、ほとんど変化がないということです。この状況にどう対応すればよいのか、ワーカーズ・コレクティブへの調査経験もふまえ、4つの項目に沿ってお話しします。
1.社会の仕組みと関係の変化
戦後の歩みのなかで、日本の社会は大きく変化しました。その変化をひと言で表すなら、「伝統的なしがらみや強制からの解放」だと言えます。これは日本に限ったことではありません。
西欧諸国における近代化は、宗教や地域コミュニティ、世襲制の職業といった束縛から個人を解放し、自由な選択を可能にしました。職業選択の自由がなかった時代、職人は親方から技術やノウハウの伝承を受け、農民はコミュニティで各々の役割を受け継ぎながら暮らしてきました。
そして日本では、地域の互助制度である「講」や「結」が、経済リスクの分散と生活の安定に重要な役割を果たしていました。
近代になり、職業を自由に選べるようになり、個の意思決定が尊重されるようになると、それに応じて自己責任の範囲が拡大し、個人の負うリスクが増大します。それを軽減するために、行政による社会福祉や社会保障といった仕組みが生まれました。それがいわゆる福祉国家ですが、「日本型福祉社会」といわれるように、日本の場合は福祉や社会保障を政府だけでなく企業や個人・地域と分担するやり方が採られました。
かつての日本では、社会と個人、国家と個人をつなぐ様々な中間団体が、個人の生活を営むうえで欠かせない存在でした。業界団体や企業も、雇用の場というだけでなく、プライベートの領域にも踏みこんで個人の生活を支えてきました。
大手企業は社宅・保養施設を独自に整備し、男性労働者を終身雇用で囲い込みました。その代わり、女性は結婚したら家庭に入り、夫を支えるべきだという価値観が強調されました。女性は労働力を再生産する装置であるとともに、介護の担い手として位置づけられたのです。
他方、日本は欧州のような失業給付や職業訓練に多くの予算をかけませんでしたが、その代わり公共事業がインフラ整備だけでなく、地域経済を下支えする役割を担ってきたのです。それは、しばしば“土建国家”と揶揄されますが、かつての日本では、公共事業は未熟労働者から専門職に至るまで、幅広い人材に雇用の場を提供する失業対策としての意味合いも強かったのです。また、政府は公共事業や各種の規制を通じて業界団体への指導を円滑に行い、企業はその庇護の下で安定的な経済活動の恩恵を受けてきたのです。
日本的社会の崩壊と新自由主義の台頭
しかし、いまや公共事業は半減し、地域経済や人びとの生活を支えてきた仕組みも崩壊しました。無原則な規制緩和によって中小企業や個人が国内外の競争にさらされ、経済成長の鈍化とともに財政赤字が拡大しました。
こうした閉塞状況のなかで、次第に各国で新自由主義的な風潮が高まっていきました。それは「“大きな政府”は非効率であり、民間に委ねたほうが経済は活性化し、サービスの質も向上する」という考え方です。1990年代以降、大店法やバス・鉄道・タクシー事業の規制緩和、建築基準法の改正などの規制緩和が進むとともに、公共サービスの民営化、民間化も進みました。ただし日本の場合、これらは必ずしも明確な戦略の下で行われたわけではなく、その背後には米国の政治的な圧力がありました。
では、その結果、政府は“小さく”なったのでしょうか? 答えはノーです。予算規模を見ると、1975年の政府歳出は20兆9千億円でしたが、2023年は127兆円に達しています。税収も過去最高を記録しています。
こうした社会の状態を『コモングッド』(東洋経済新報社2024)という著書で指摘したのが、米国の経済学者ロバート・B・ライシュです。コモングッドとは、個人の利益でなく、コミュニティ全体の利益のために自発的に守るべきものという意味です。彼は、それが金儲けのために破壊され、相互扶助や社会規範で成り立ってきた秩序が崩壊していると嘆いています。
日本も例外ではありません。病気などで自立した生活ができなくなれば、社会保障や福祉といったセーフティネットがあり、元気になったらまた働けるようにサポートを受けるという社会契約が、小さい政府という旗印の下で、いつの間にか書き換えられていたわけです。これでは、個人を支える基盤は先細りするばかりです。
こうして普通の市民が生きにくくなり、様々な社会のひずみが生じるなか、改めて非営利組織が注目されているのです。
(P.62-P.65 記事抜粋)