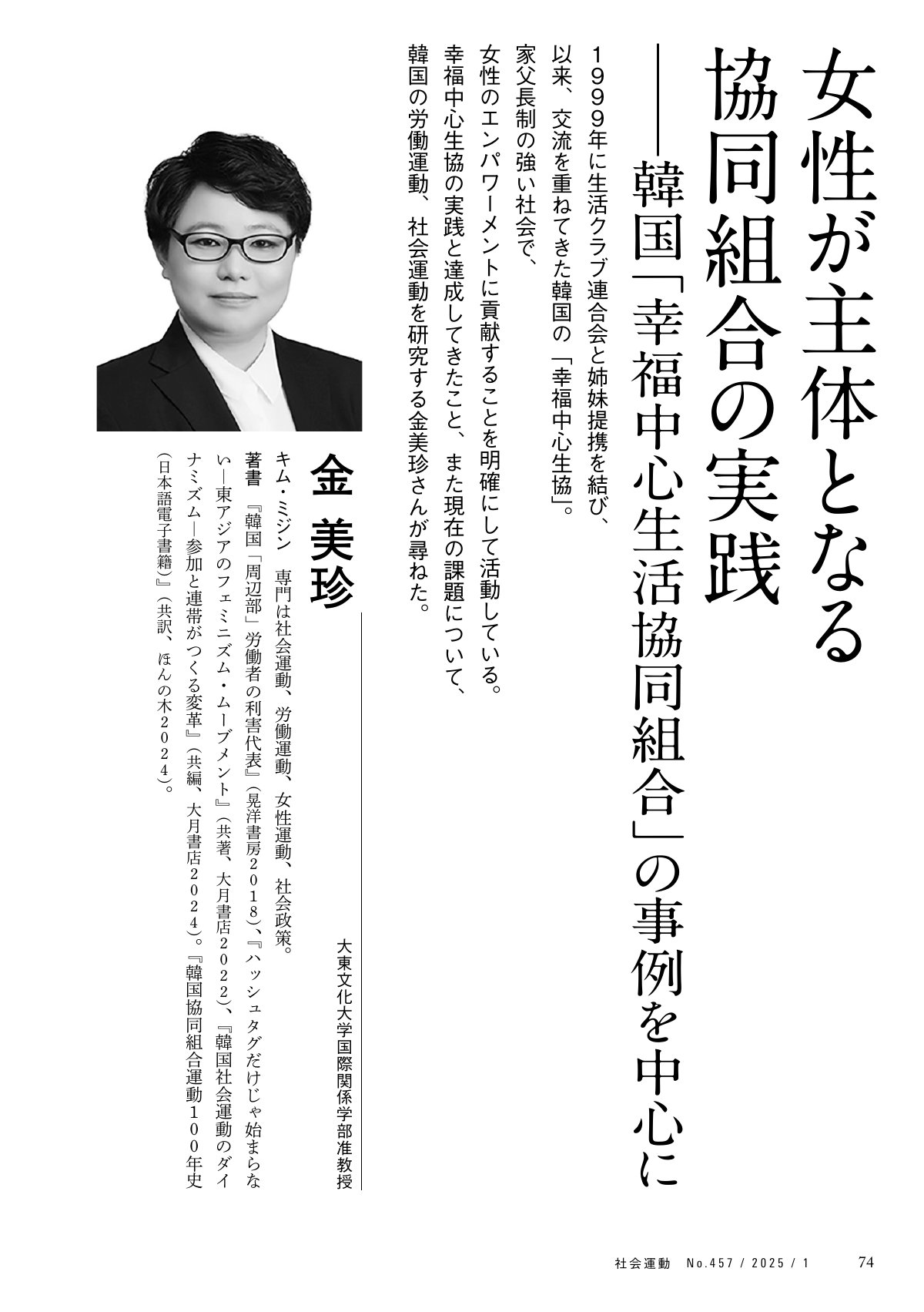③女性が主体となる協同組合の実践 ―韓国「幸福中心生活協同組合」の事例を中心に
金美珍 (大東文化大学国際関係学部准教授)
はじめに
相互扶助と互恵の原則に基づく協同組合は、すべての人々の人権とジェンダー平等の実現を目指している。国際協同組合同盟(ICA)は1995年「協同組合におけるジェンダー決議案(Gender Equality in Co-operatives)」を採択した以降、2000年「ジェンダー平等促進のためのICA戦略(ICA Strategy for Promoting Gender Equality)」、2010年協同組合を通じて女性のエンパワーメントが強化できるという「国際協同組合の日メッセージ」を表明するなど、ジェンダー平等の実現を主な目標としてあげてきた。
ところで、ジェンダー平等に向け女性のエンパワーメントを達成していく協同組合の実践とはどのようなものであるのか? 本稿では、女性運動の一環として設立され、女性が主体となって活躍してきた韓国の「幸福中心生活協同組合(以下、幸福中心生協)」の事例を中心に、その実践について述べていく。
Ⅰ.幸福中心生協の略史
幸福中心生協は、ジェンダー平等の実現に向け1987年に設立された韓国女性民友会(以下、民友会)というフェミニスト女性団体によって発足された。初期、民友会は大衆的な女性運動を目指し、主に働く女性の問題を取り上げていた。だが、生活の中でジェンダー平等を実践していく主体として主婦にも注目していたので、民友会の中に「主婦分科」も設けていた。主婦分科のメンバーの中には、家事と両立しながら地域の問題を解決でき、大量消費がもたらす弊害に対応する生協運動のオルタナティブな性格に関心を持っていた人もいた。主婦分科の消費者問題委員会が中心となって生活協同組合発起委員会(約20人)を構成し、1989年8月から民友会では生協設立の準備が始まった。民友女性学校や地域で会員を対象にした教育、出資金の募集、事業計画及び予算案づくり、事務室と倉庫の設置など約1年間の準備を経て、同年12月「ともに歩んでいく生活協同組合」(以下、民友会生協)を設立した。
設立初期、民友会生協は民友会とは独自的に運営されていた。だが、1991年約700万ウォンの赤字が発生したことをきっかけに、1992年1月から民友会内部の生活共同事業部という一部署として統合され、民友会の各部署及び組織全体で、生協事業を分担していた。具体的には、生協の総会が民友会の総会へと統合され、理事会の役割は中央委員会、運営委員会、生協委員会に、購買供給の業務は生協事業部に、組織・教育・広報は民友会本部の事務局と支会に分担されていた。地域の民友会は会員を対象にした教育とともに、生協と関連する生活財の開発や供給品目の拡大を担い、生協事業部がサービス全般の改善を担当した。
韓国で消費者生活協同組合法が制定された1999年の翌年、民友会生協は生協法人となった。これをきっかけに民友会と民友会生協はそれぞれ別途の総会と理事会を構成した。これに伴い、教育、広報、購買と物流事業が生協に一元化された。2003年から、民友会生協は地域の支部が独自に理事会と事務局を運営する単位生協へと組織変化をすすめ、2006年から、東北・南西・高陽の3地域で単位生協を立ち上げた。地域を基盤とする単位生協の増加に対応して、組合員の活動空間として単位生協の機能を忠実化し、協同組合原則に忠実な共同購入事業のモデルをつくり出すために、2011年「女性民友会生協連合会」(以後、幸福中心生協連合会)を発足させた。現在、幸福中心生協連合会には、高陽、坡州、ソウル(東北、龍山)、鎮海など10地域の単位生協と生産者会が会員として加入している。
(P.75-P.76 記事抜粋)