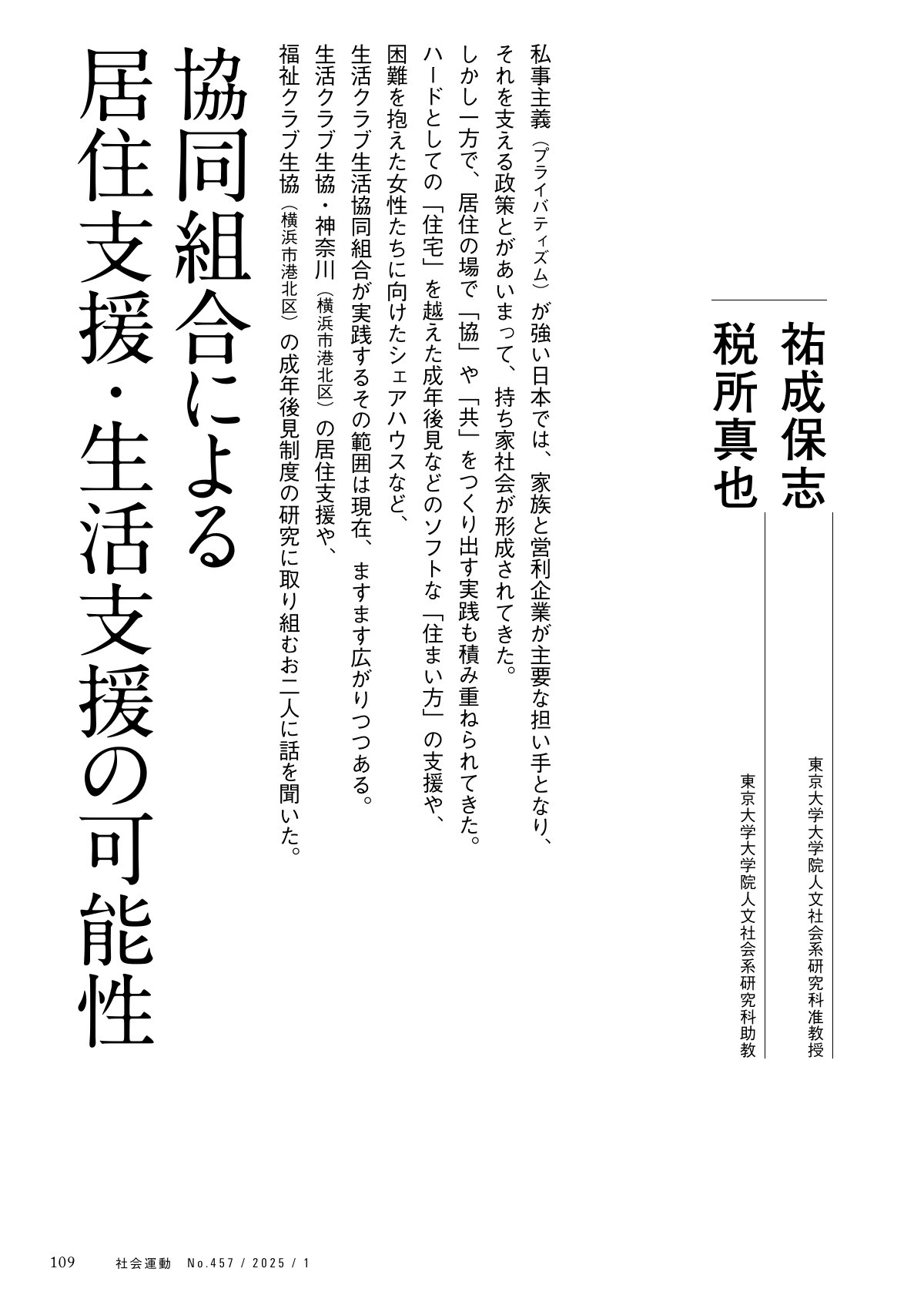③協同組合による居住支援・生活支援の可能性
祐成保志(東京大学大学院人文社会系研究科准教授)
税所真也(東京大学大学院人文社会系研究科助教)
居住支援はどう広がってきたか
祐成 政府の審議会や委員会などの文書を見ていくと、1980年代くらいからその後の居住支援に連なる考え方が出てきます。「居住支援」という用語自体は、2001年の「高齢者住まい法」に設けられた「高齢者居住支援センター」の規定が最初かと思いますが、「居住支援協議会」について定めた07年の「住宅セーフティネット法」によって広まりました。
この数年、住宅政策は大きな曲がり角を迎えています。前岸田内閣が設置した「全世代型社会保障構築会議」は、2022年12月に発表した報告書で「住まい政策は社会保障の重要な課題」であると提言しました。これは、住宅政策と社会保障の関係を組みかえる、画期的な位置づけのし直しなの ではないかと考えています。これまで日本の社会保障においては、住宅政策は社会保障に「関連する」制度ではあっても、社会保障そのものではないというのが一般的な位置づけでした。ここで注目したいのは、提言が住宅政策ではなく「住まい政策」と呼んでいる点です。小さな違いに見えるかもしれませんが、住宅という「モノ」の供給よりも、住まうという「コト」(行為・状態)をどう支えるかが課題となっているという現状認識が背景にあるのだと思います。
ではなぜ住まいが社会保障制度の課題とされるようになったのか。すでに1987年には自治体で公営住宅などにライフサポートアドバイザーをおいて、高齢の入居者にサービスを提供する「シルバーハウジング」という仕組みが始まりました。この頃から住宅の供給と高齢者の生活支援を組み合わせるという発想が生まれていたのです。
また、2000年に介護保険制度が開始されたことがこの発想の広がりに大きく影響していると私は考えています。介護保険の導入によって、それまでは家族が担っていた介護サービスへのニーズが顕在化するに従って財政規模は拡大し、制度を運営する側は危機感を抱きました。そこで介護施設に頼るのではなく、在宅で過ごせる期間を延ばす必要があると考えたのです。在宅と特別養護老人ホームをはじめとする施設の中間に位置する「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」のような仕組みを設けて、一つの緩衝材にしていくという発想です。いわば介護保険制度を持続可能なものにするための居住支援です。
しかし2010年代には、より低所得の人、あるいは複合的な困難を抱えた人の住まいをどう確保するかが課題となって、「生活困窮者自立支援法」に居住支援にかかわる仕組みが取り入れられます。このとき、人が仕事と同時に住まいも失うという事態に対応すべく、公的な住宅手当として住居確保給付金が導入されました。しかし制度が運用されるにつれて、支援の現場から、高齢で困窮している人がカバーできないという問題が提起されるようになります。2010年代の終わりくらいから、いよいよ世代を限定せずに居住困難に対応する仕組みが必要だという考え方が受け入れられやすくなっていったのです。
(P.110-P.111 記事抜粋)