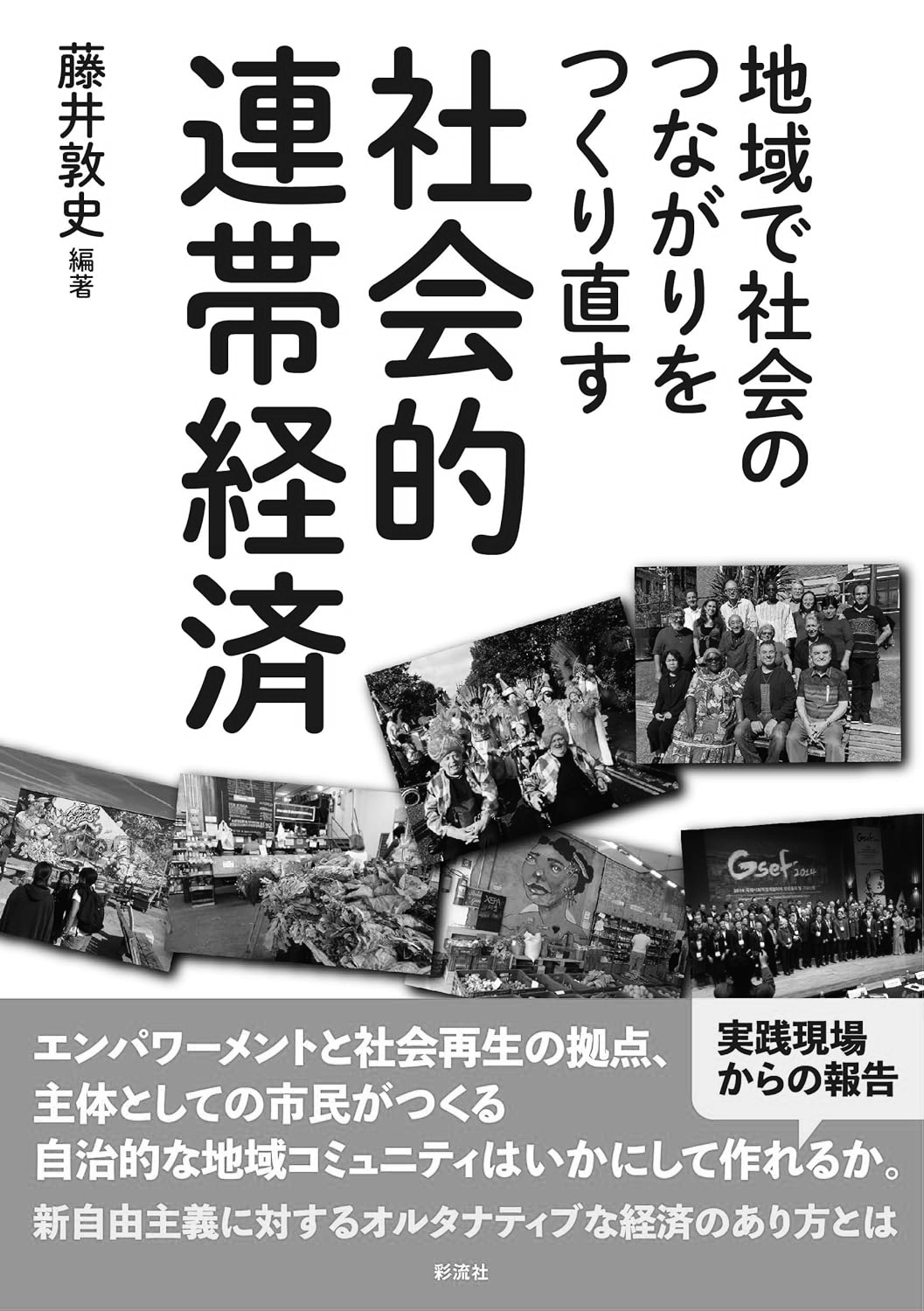書評①『地域で社会のつながりをつくり直す社会的連帯経済』 藤井敦史 編著(彩流社2022年)
オルタナティブな働き方で経済を変容させていく
労働とは、苦痛の対価として生活のためにお金を稼ぐこと。そんな感覚を多くの人が抱いて働いています。国の政策によって市場原理主義を重視した大幅な規制緩和が推し進められ、日本では90年代終盤からパート・アルバイト・派遣などの非正規雇用が増えつづけ、今や働く人のうち約4割を占めています。社会保険を含む税金は重くなる一方で、正規雇用と比べて賃金が低く貯金はできず、突然の解雇や病気をきっかけに貧困に陥る人も少なくありません。コロナ禍の打撃も深刻です。働いても働いても収入が増えない就労条件が定着し、6人に1人が相対的貧困(現在、世帯年収127万円が基準)という負のスパイラルが止まりません。いつでも首を切れる非正規雇用は企業にとっては有利ですが、雇われる身は常に不安定。人の尊厳を蔑ろにする労働搾取により、人生が脅かされる状況は日本の外でも広がっています。
こうした弱肉強食の新自由主義的な資本主義に対抗し、オルタナティブな経済を作り出そうとする運動の概念が「社会的連帯経済」です。本書には、先進的な試みも紹介されています。例えば、ブラジルのサンパウロにある店舗「自由の市」では、値札に記されているのは原価で、店舗運営にかかる詳細な経費が提示されて35パーセント上乗せの代金を求められますが、経済的事情のある人は減額交渉ができます。
一方、米国のミシシッピ州ジャクソン市には近隣住民が任意で野菜を栽培できる「自由農園」があり、公共交通機関がまともに機能しない町で車のない貧困層の買い物難民も新鮮な野菜を手に入れられます。いずれも、経済危機や貧困拡大を背景に、失業者や脆弱階層の自活支援のために市民の支え合いから生まれてきた連帯の仕組みです。
韓国ソウル市では、市民活動家で弁護士だった故・朴元淳氏が2011年に市長になり、福祉、住居、学校給食、エネルギーなど様々な分野で、多様な住民が参加する「コミュニティ協同組合」が事業運営できる画期的な枠組みを推進し、社会的連帯経済が飛躍的に発展して根づきました。
(P.144-P.145 記事抜粋)