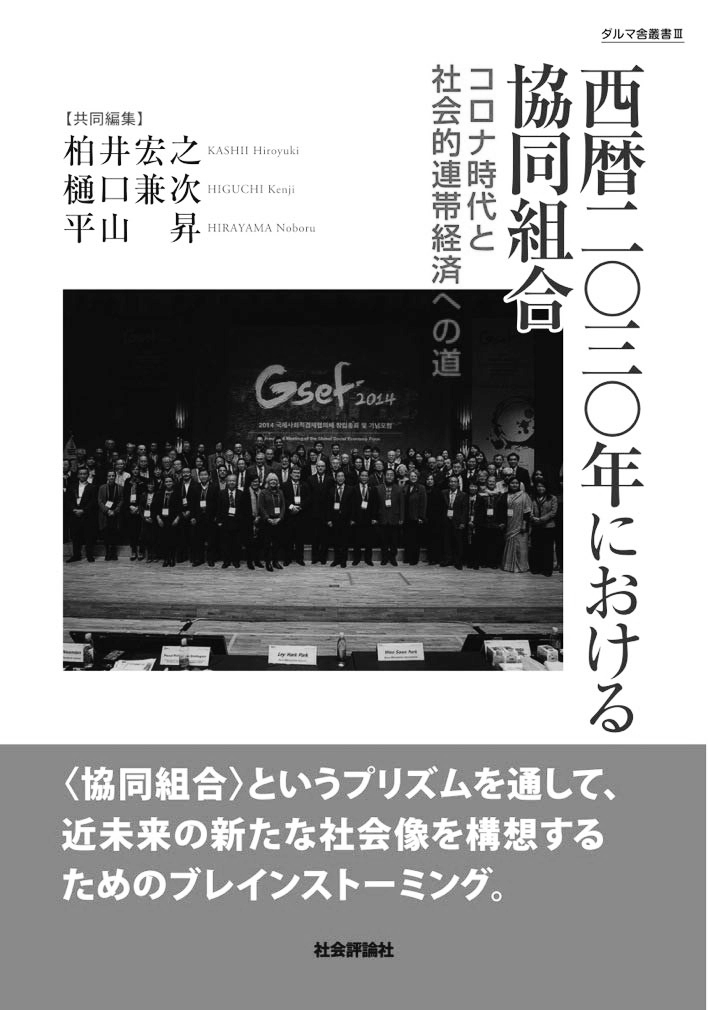書評②『西暦二〇二三年における協同組合』 柏井宏之 樋口兼次 平山昇 編(社会評論社2020年)
新時代再構築の模索ないし挑戦の試み
本書は、タイトルにある2030年を目途に協同組合ビジョンを示した意欲作である。この年は、国連のSDGs(持続可能な開発目標、2030アジェンダ)の達成年でもある。そして本書は、前世紀後半に出された『西暦2000年の協同組合』(通称レイドロー報告、日本経済評論社1989)を意識したもので、協同組合が時代に翻弄されてきた中で、新時代に向けて再構築を展望しようとの試みでもある。
20世紀後半、東西対立・冷戦終了の時代、協同組合への期待は大きく浮き沈みしてきた。とくに経済のグローバル化と市場原理偏重の新自由主義が蔓延して、社会的格差と脆弱層の増大が進行した。その受け皿として、協同組合のみならずNPOや社会的企業などサードセクターと呼ばれる、対抗的動きへの期待や関心が高まりをみせたのだった。それは対抗なのか、補完なのか、時代状況としては紆余曲折をへてきた。
大富豪が続出しだす強欲資本主義の時代と言われ出したその矢先、世界金融危機(リーマンショック2008年)に陥ったことで、まさに資本主義経済の脆弱性があらわになったのである。日本でも派遣切りが横行し「年越し派遣村」が話題を呼んだ。大量失業が蔓延する世界状況下、解雇や倒産が続出する中で多少とも影響が軽微だったのが協同組合セクターだったこともあって国連は、2012年を国際協同組合年と定めた。ユネスコの協同組合の無形文化遺産登録(2016年)もあり、その存在意義が高く評価されたのである。
その再構築と未来を見すえた展望
環境危機や貧困問題が深刻化するなかで、国連は2000年代に入り南北問題・貧困撲滅を掲げてMDGs(ミレニアム開発目標、2015年目標年)を打ち出し、その後も地球市民を意識した2030アジェンダ・SDGsを掲げて、いまに至っている。MDGsからSDGsへと推移するなかで、国家というアクター以上に、自治体・企業・市民・NGO・協同組合などの役割を重視する流れが続いてきた。なかでも象徴する動きとして、国連が2025年を国際協同組合年に再度定めたことは、その期待の大きさを示している。
しかし、世界の労働人口の約1割を占める協同組合と言っても、その実態は決して一枚岩ではない。資本主義経済の矛盾への対抗とは言っても、補完ないし下請け的役割の部分もあり、なかなかオルタナティブ(代替)の側面を切り拓く潮流としては、まだまだ模索状況にある。
(P.146-P.147 記事抜粋)