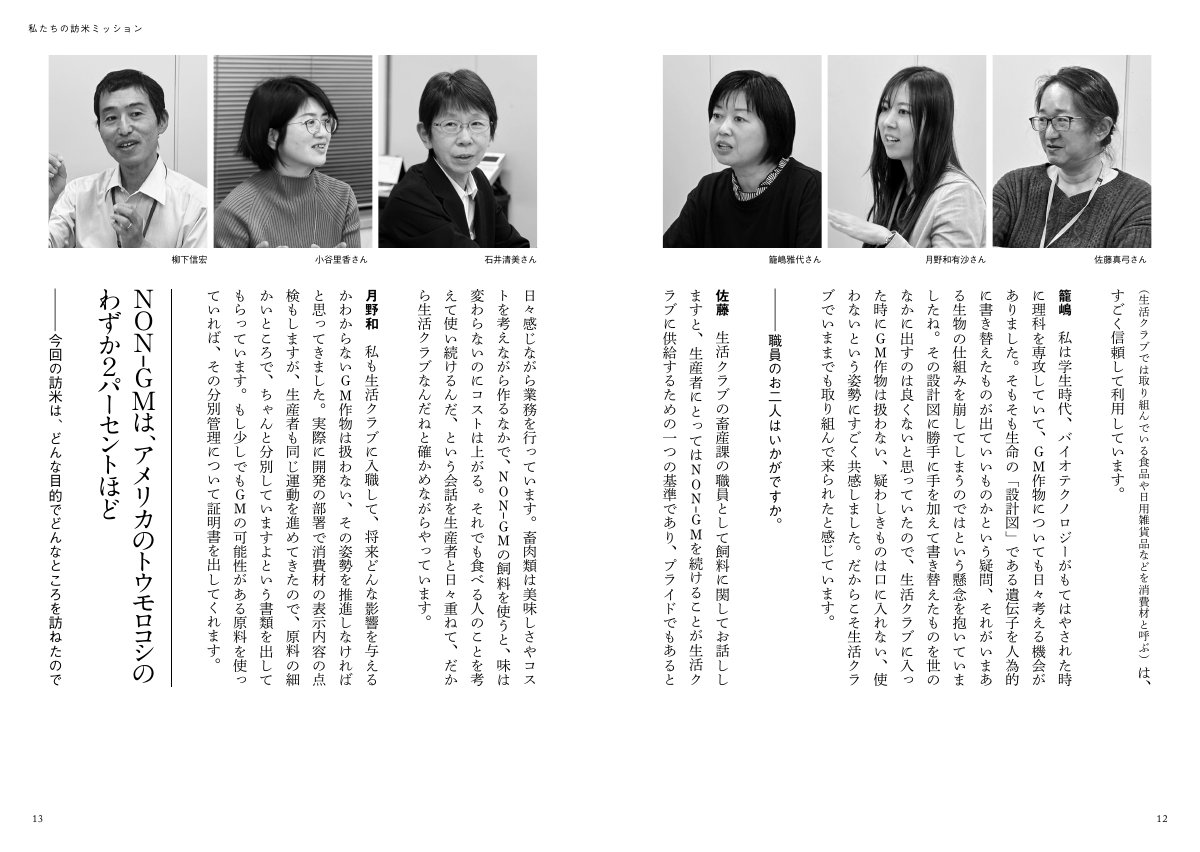●私たちの訪米ミッション
生活クラブ生協・埼玉理事長 石井清美/生活クラブ生協・都市生活理事長 小谷里香
生活クラブ生協・神奈川副理事長 籠嶋雅代/生活クラブ連合会 加工食品・生活文化部 食品課課長 月野和有沙
生活クラブ連合会 ビジョンフード推進部 畜産課課長 佐藤真弓/進行 市民セクター政策機構理事長 柳下信宏
【発売中】季刊『社会運動』2025年4月発行【 458号】特集:食の自治の可能性を拓く 瀬戸際にある飼料とNON-GMO
長期の供給協定を結ぶからには、私たちにも責任が
―「長期種子供給協定」(下図参照)の契約では、私たちも「NON-GMの需要はありますから、種子を作ってください」と約束することで、責任が生じるわけです。例えばベックス社とは6年先までの契約ですが、長期協定はそれだけ責任も重いと思っています。というのも、種子を育てるのに1年かかり、できたトウモロコシが日本に輸入され、次の年に家畜に与え、大きくなった家畜を私たちが食べる。2031年のトウモロコシの種子を家畜に与え、実際に組合員が肉として食べるのは34年なので、10年先まで約束することになります。みなさんは今回の視察でどのように考えましたか。
小谷 ベックス社の方からも、「種子開発には本当に時間がかかるので、長期に協定を結んでもらうことはありがたい。NON-GMを継続していきたい」と意思表示してもらえたので、私たちがしっかり食べ続けなければと思いました。それが社会にどう影響していくかを噛み砕いて伝え、理解して使う人を増やす地道な組合員活動がもっと必要でしょう。それと核になる人を作っていくことですね。いま、給料は上がらないのに物価が上がり、NON-GMのエサを食べた牛や豚のお肉を使いたくても使えない人が増えている。そのなかで継続して私たちの責任を果たしていくには、食べる口を増やして「月に1回でもいいから買うよ」と言える人を組合員活動で作ることです。基本的なことですが、生産者の話を聞く、学習会をする、伝えることで自分のなかの理解を深めるなどですね。
籠嶋 食べる人がどこまで産地のことを想像できるかが、すごく大事ですね。目の前のお肉にそれだけの時間と空間が必要で、多くの人が携わっていること。実際に見た人、聞いた人、知っている人が、美味しいのはもちろんですが価値を伝えて、食べる人たちを増やしていく必要があると思います。
小谷 一方で、いまは組合員活動に参加する人がすごく減っていますね。来てもらって直接伝えられるともっといいのですが、そうでない参加の仕方や方法を考えないといけないでしょうね。食品の向こうにある世界をどこまで考えられるか、という想像力はすごく大事なことだし、生活クラブは気づきを得られる貴重な場だと私は思っているので、そこに参加する人を作って増やしたい。私は、面白さを伝えるのも「あり」だと思います。組合員活動の面白さというか、ただの肉じゃなくて、肉から広がる世界が見えるともっと面白いなと思いますし、それを会社ではなく組合員がやっている。「最初は遺伝子組み換えを知らなかった人がこうなる場なんですよ。わかることって面白いんです」と。お金で買えないものを得られることを伝えたいですね。
―みなさんの話にも出ていましたが、飼料、特にNON-GMで分別管理しているエサは価格が上がっています。そのことが生活クラブの消費材の価格につながり、利用するのも厳しい。トウモロコシはNON-GMを堅持しても、大豆かすは一部の生産者で不分別のものに切り替えざるをえなくなっています。ここをどう考えていけばいいでしょうか。
石井 今回のミッションの最後に、参加したメンバーで「生活クラブは社会運動なんだ」と確認し合いました。そこにつながっていく動きをつくるのが必要じゃないでしょうか。「わかって食べる人を作る」というフレーズが使われるように、組合員に伝えるときに自分が食べるものをどう考えていくかがポイントだと。国内で飼料を調達することは未来図でもあるのですが、ただ現状を考えるとそれはかなり難しい。さらに食事の内容が昔と変わってきて、畜肉がない食生活をいまの人たちは受け入れられないでしょう。ですからIPハンドリングでトレースができる海外の飼料を考えていいと思うんです。
籠嶋 コストが上がったことで、一人がたくさん使うのが難しいのなら、少しずつ使う人を増やすほうが現実的だと思います。うまく調理する、美味しく食べる方法や知恵を私たちはいろいろ持っているし、活動のなかで提案できますね。
(抜粋)