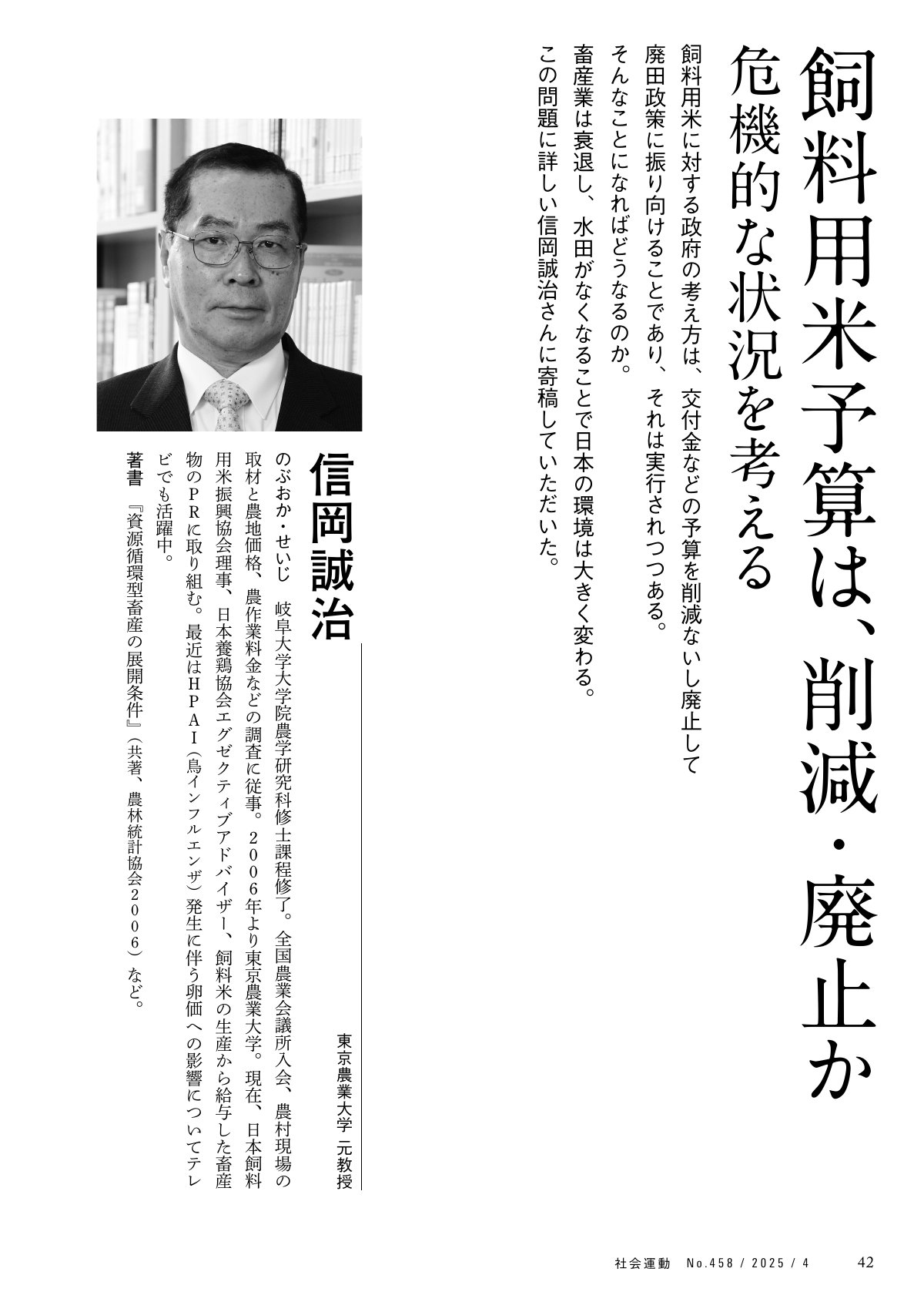●飼料用米予算は、削減・廃止か
(東京農業大学元教授 信岡誠治)
【まもなく発売】季刊『社会運動』2025年4月発行【 458号】特集:食の自治の可能性を拓く 瀬戸際にある飼料とNON-GMO
1. 飼料用米とは何か
国が戦略作物として助成
飼料用米は、全国に拡がる水田を活かしながら飼料用のコメを増産し国産飼料の原料として利用するものである。この飼料用米は行政用語で、政府により水田活用の直接支払交付金の対象として戦略作物助成が行われているものが該当する。戦略作物助成による飼料用米への交付金は収量に応じて10アール当たり5・5万円~10・5万円(認められた多収性品種の場合)、ただし飼料用米が食用米の一般品種の場合、2025年産は標準単価7万円/10アール(5・5~8・5万円/10アール)、2026年産は標準単価6・5万円/10アール(5・5~7・5万円/10アール)とすることが決まっている。
現在、飼料米として主に利用されているのは飼料用米であるが、この他に従来から食用米生産に伴って発生するクズ米や、政府から払い下げられる国産の備蓄米(玄米)や輸入のMA(ミニマムアクセス)米(日本が海外から最低限輸入しなければならない米)も飼料米として利用されている。
備蓄米やMA米は本来人間の食用米であるが、備蓄や保管の期限がきたものは、不定期的に在庫処分として払い下げられ配合飼料に混ぜられて家畜に給与されているわけである。
飼料用米が政策的に認知され生産が本格化してきたのは、2008年からである。皮切りは飼料用米導入定着化緊急対策事業として、全国49箇所で「飼料用米利活用モデル実証」がスタートしたことである。
端緒を開いたのは生活クラブを軸としたプロジェクト
飼料用米は全国に拡がる水田を活かしながら飼料用の米を国産飼料の原料として利用するもので、この端緒を切り開いたのは、生活クラブを軸とする山形県での「飼料用米プロジェクト」である(写真1)。
生活クラブの提携生産者である平田牧場(養豚)、JA庄内みどり遊佐支店と、遊佐町、山形大学、生活クラブ連合会などが連携して2004年から取り組んできた同プロジェクトは「自給率向上のモデルをつくる」をスローガンに飼料用米の作付拡大に取り組み2007年には230戸の稲作農家が参加、面積は130ヘクタールに拡大し生産量も690トンに達し、平田牧場の肥育後期の肉豚の給与飼料の10パーセントを飼料用米にして「こめ育ち豚」のブランドで生協の組合員に届けられた。この取り組みが国にも着目され、国による飼料用米の全国展開につながったわけである。
そして、2009年の民主党へ政権交代後は戸別所得補償制度のモデル対策として水田利活用自給力向上事業が打ち出され、新規需要米(米粉用・飼料用・バイオ燃料用、WCS用稲〈稲穂と茎葉をまるごと刈り取り、フイルムでラッピングし乳酸発酵させた牛の飼料〉)に対して10アール当たり8万円を直接支払いにより交付されることとなり、飼料用米の作付面積は急拡大してきた。
その後、自民党政権になってからは現在の戦略作物助成の体系に変更され、収量払いを基本とした交付金となっている。
(抜粋)