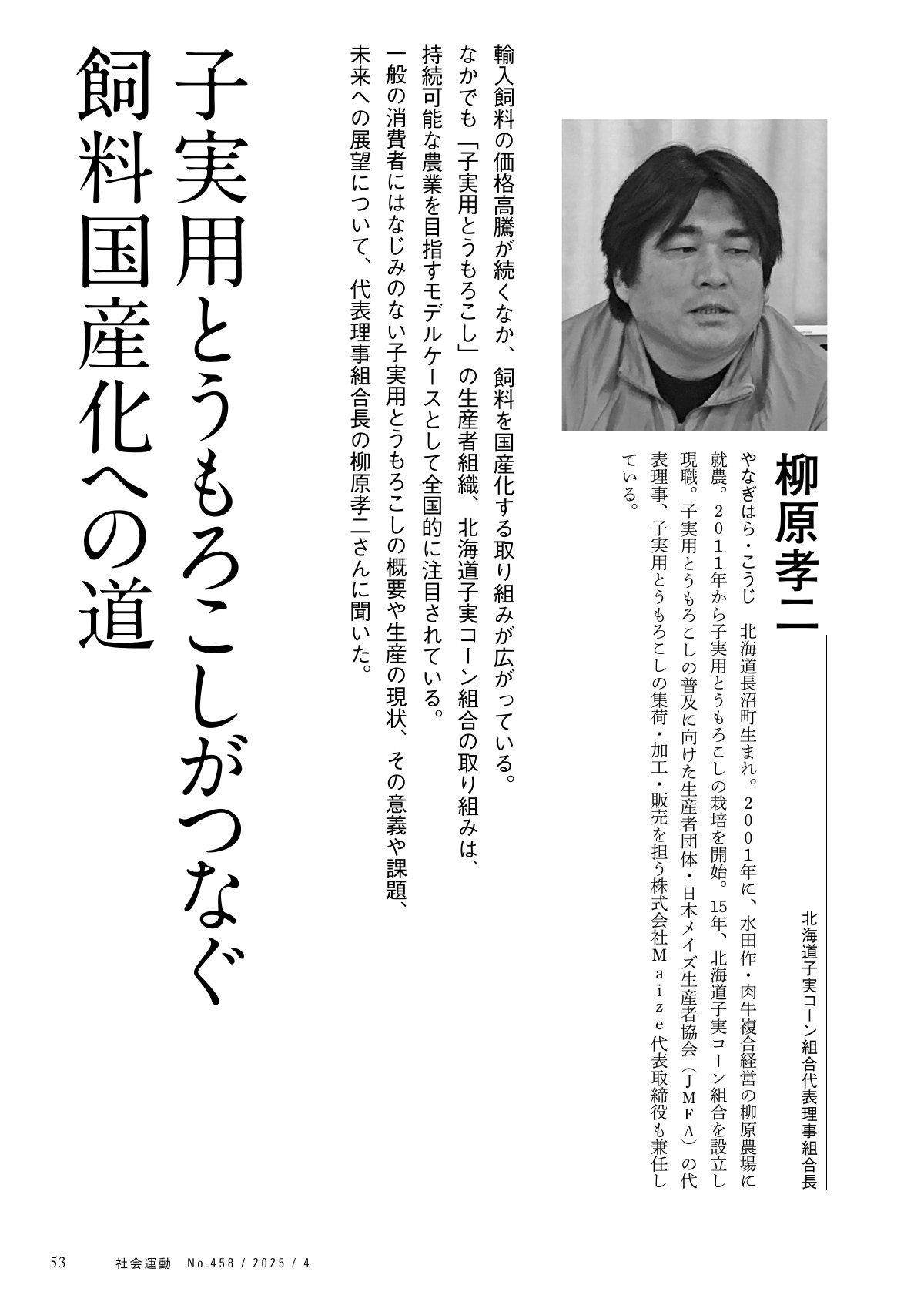●子実用とうもろこしがつなぐ飼料国産化への道
(北海道子実コーン組合代表理事組合長 柳原孝二)
子実用とうもろこしは世界的に重要な穀物
子実用とうもろこし(以下、子実コーン)は、完熟したとうもろこしの実だけを収穫して乾燥させ、家畜の飼料などに利用される穀物。主に用いられる品種はデント種やフリント種で、一般の食料品店に並ぶスイートコーンとは別物だ。
子実コーンの用途は多岐にわたる。ほぼすべての家畜の濃厚飼料(栄養源となる飼料)になるほか、スナック菓子、シリアル、コーンスターチ、コーンシロップ、ウイスキー、コーン茶などの食品・飲料や食品添加物、バイオエタノール、接着剤、製紙原料など工業用にも利用され、世界で最も多く栽培されている穀物のひとつとなっている。アメリカ・シカゴの穀物相場で先物取引される「コーン」も、この子実コーンを指している。
「近年の日本における子実コーンの需要量は、年間約1500万トンで推移しています。うち約1100~1200万トンが飼料用で、残りの300~400万トンが食品や工業用です。主食用米の需要量は年間で約680万トンですから、子実コーンの国内需要量が、いかに大きな数字かおわかりいただけるかと思います(図1)。にもかかわらず、国内の栽培面積はごくわずかで、米を主食とするタイやフィリピンなどに比べても極端に少ない。ほとんどを輸入に頼っているのが現状です(図2)」(柳原孝二さん・以下同)。
日本でも昭和40年代までは子実コーンの栽培が行われていたが、その後、ほとんど作られなくなったという。理由のひとつは、戦後、畜産農家の規模が急激に拡大したことだ。
「戦前は田んぼや畑をやりながら家畜も飼うといった小規模な畜産農家が多かったのですが、戦後、状況は変わりました。畜産は天候に左右されにくく、飼料さえ確保できれば安定した生産が可能で、人材雇用や大規模化もしやすかった。食肉需要の拡大とともに、戦後50年間でおよそ50倍になったといわれます。一方、耕種農家(田畑を耕して米、野菜、果物、花などを栽培する農家)は数倍にしかなっておらず、耕種農家と畜産農家の分化が進み、自家用飼料を生産する機会は減少。畜産農家は安価な輸入穀物に依存しながら安定的に畜産物を生産して規模を拡大するというスタイルが一般化し、国内で飼料を調達する仕組みは途絶えました」
子実コーンの供給を輸入に依存する危うさ
近年では、ウクライナ情勢や為替相場、気候変動の影響や、北米を中心としたバイオエタノール原料としての利用増、中国などの需要拡大などにより、子実コーンの国際価格が上昇。それにともない国内の配合飼料価格も上昇し、高止まりの状態が続いている。柳原さんは、輸入依存型の供給システムそのものの危うさも指摘する。
「子実コーンは、アメリカなどの主要な生産国から貨物船で日本各地の港に運ばれます。ここ道央では苫小牧港が一大拠点です。船が港に着くと、子実コーンは掃除機のようなもので吸い上げられ港湾サイロに入ります。その背後には飼料会社の工場が並んでおり、子実コーンはサイロから直接コンベアーで運ばれ、次々と飼料加工されて畜産農家へ配送されます。
こうした仕組みは一見合理的ですが、大きなリスクも抱えています。子実コーンの収穫は、海外でも基本的には年に1回です。それを各農家がサイロで保管し、日本へ毎週のように出荷してくれるおかげで、現在の供給システムが成り立っています。港湾サイロの保管能力は、年間需要量に対し1~2カ月分くらいしかなく、災害や戦争などで輸送ルートが遮断されれば、すぐに飼料不足に陥る危険性があるのです」
(抜粋)