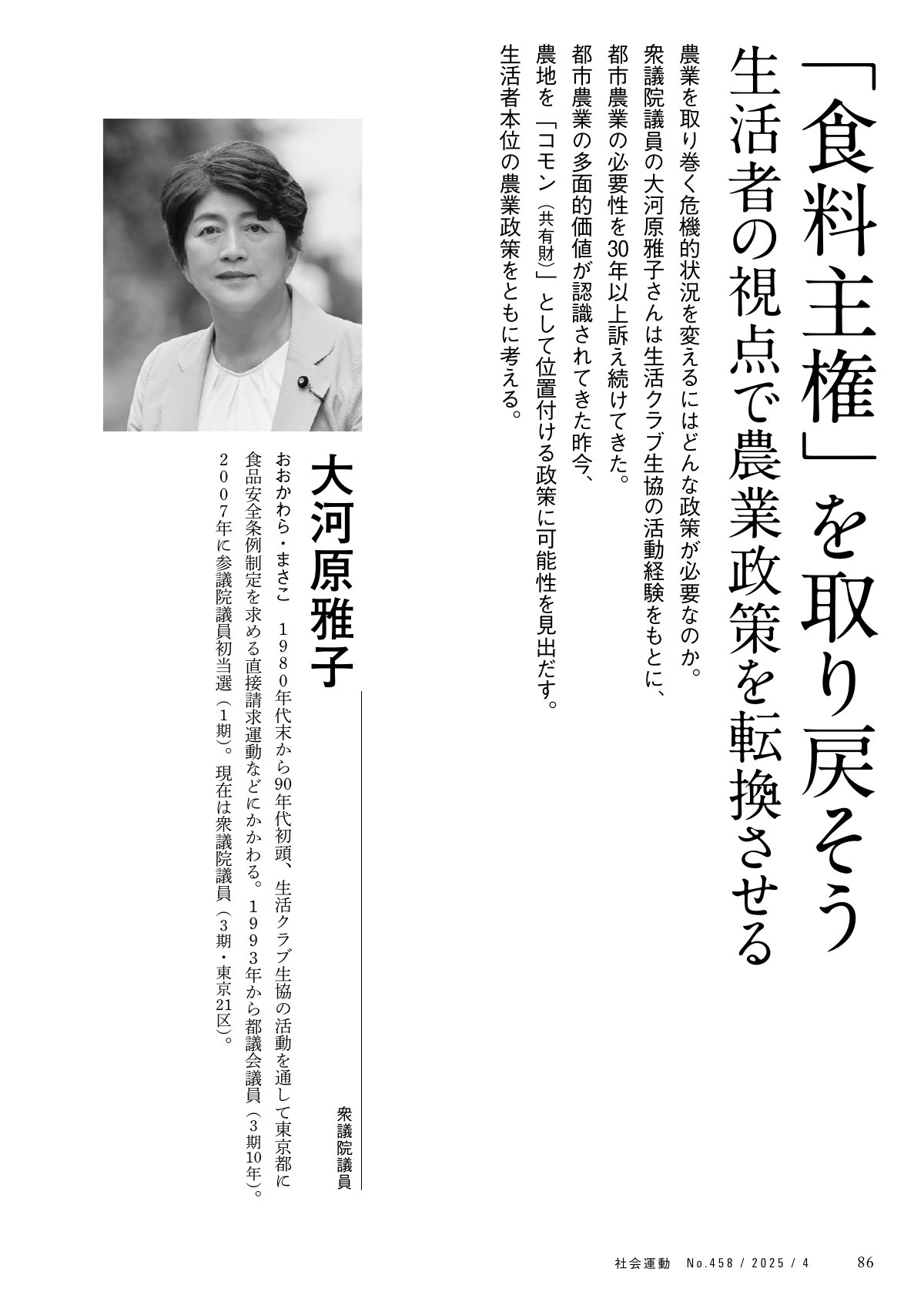●「食料主権」を取り戻そう
(衆議院議員 大河原雅子)
【発売中】季刊『社会運動』2025年4月発行【 458号】特集:食の自治の可能性を拓く 瀬戸際にある飼料とNON-GMO
日本農業の危機を乗り越えるために直接支援を
―現在の日本の農業をどのように見ていますか。
いま国会では農林水産委員会に所属していないので農業政策について発言する機会はあまりありませんが、農業と食の現状に大きな危機感を抱いています。近年、「地球沸騰化」とまで言われるほど気温や海水温は上昇し、豪雨、干ばつなどの異常気象が、世界でも日本でも頻発し、食料生産に甚大な影響が出ています。私がずっと懸念してきた気候変動危機は、現実的な脅威となりました。
2024年秋には店頭から米がなくなる緊急事態となり、日本の食料安全保障政策に重大な問題があることが明らかになりました。コロナ・パンデミックとロシアのウクライナ侵攻の影響が長引き、食料だけでなく農業資材や燃料価格の高騰は深刻です。日本の食料自給率(カロリーベース)は38パーセントですが、ハウスやマルチなどに使われる農業資材、肥料、施設栽培の暖房や農業機械の燃料は輸入に頼っており、もはや国民が安定的に食料を確保できる状況とは言えません。長年にわたって政府が自給率を軽視し、農業の持続可能性をないがしろにしてきた結果です。
―2008年の民主党政権では戸別所得補償制度で農業者への直接支援に踏み切りましたが、この政策はどのようなものだったのでしょうか。
食料を生産するには、きれいな水、土壌、空気などの環境と、安全で良質な種子、そして農家が安定して生産に従事できる所得保障が不可欠です。農産物は、気候等に収穫が左右されるので市場価格の変動が大きく、経済優先を過度に進める新自由主義社会の競争下では厳しい状況に追い込まれてしまいます。ですから、食料の安定的な確保を図るには農業を公費で支える必要があります。2008年に民主党政権で導入した「農業者戸別所得補償制度」は、直接支払いの制度で農家の方々からの評価は高かったのですが、自民党政権が復活して「経営所得安定対策制度」となり交付金が削減され、2018年に廃止されました。気候変動危機がますます高まり、資材やエネルギー価格の高騰が長期化するいま、農家の窮状を直接支える仕組みをきちんとつくり直すことが急務です。
日本政府は大規模化とITを活用した「スマート農業」を優先する政策を進めていますが、画一的な大規模農業を押し付けるのではなく、地域の特性と農産物の適性を見極めた細やかな政策が求められます。消費者は、生産者の現状をよく知り、なぜ日本の農業がこれほど厳しい状況にあるのか、どのような政策が行われてきたかを考え、政治を変えていくことが必要です。消費者が声をあげ、生産者とともに行動し、命と健康を守るために農と食のあり方を正していかなければなりません。
この30年、消費者と生産者の関係性が見えにくくなり、人と食の距離が遠くなってしまいました。農業従事者の高齢化と後継者不足が進む現状に、多くの消費者の目は向いていません。80年代から貿易自由化による関税引き下げが進められ、TPP(環太平洋パートナーシップ)など自由貿易協定が推進された結果、食料の輸入がさらに進み、日本の農業はどんどん脆弱化しています。
その一方で、大企業が支配する経済優先のグローバル・フードシステムが市場に根づき、生産者・流通業者・消費者、それぞれの立場からも、食の安全性や品質を守ることがどんどん難しくなっています。さらに2018年には種子法が廃止され、主要農産物すら自分たちの手で持続的に生産できなくなってしまいました。「食料主権(food sovereignty)」を十分行使できていない状況にもっと危機感を持つべきです。
(抜粋)