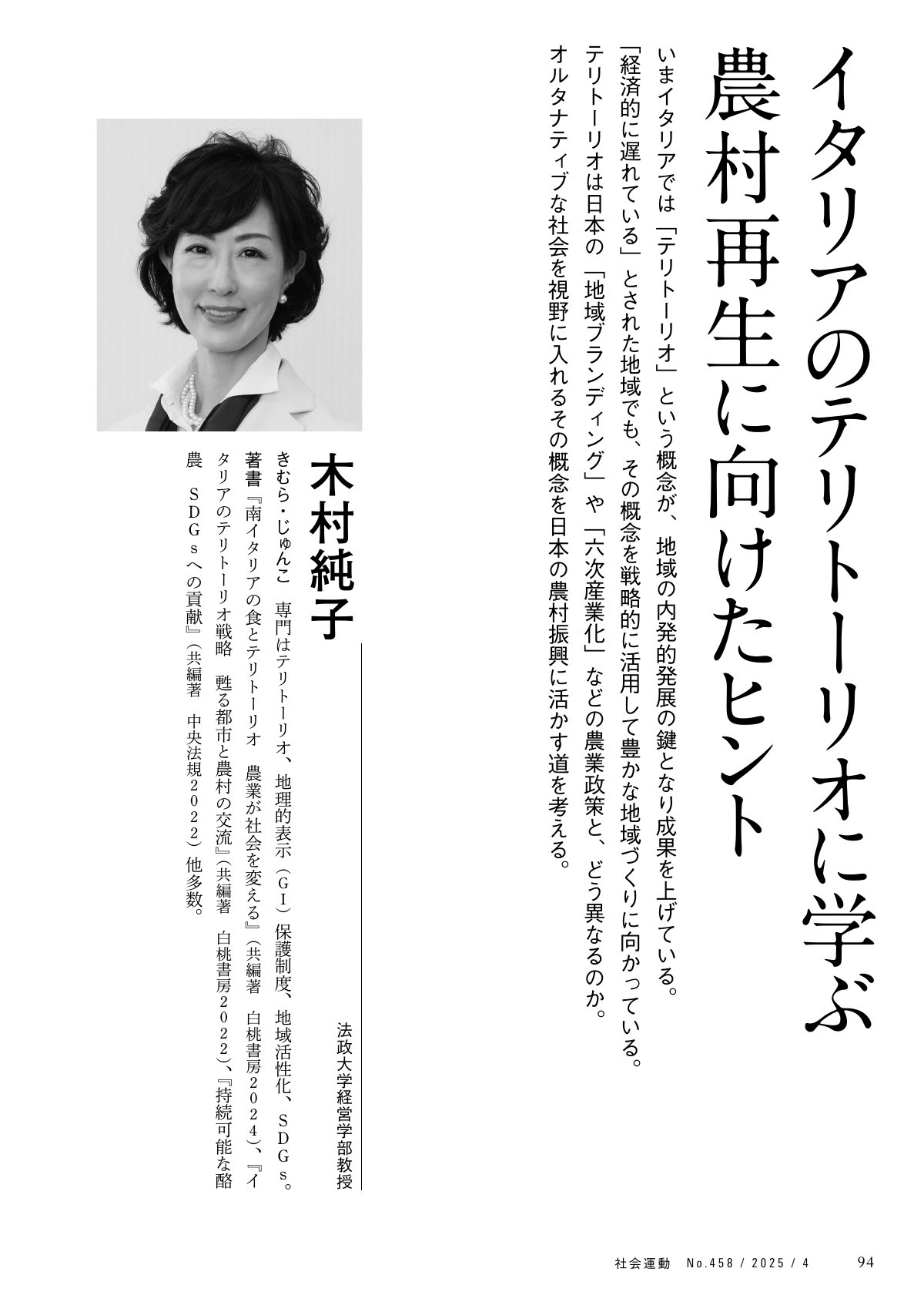●イタリアのテリトーリオに学ぶ農村再生に向けたヒント
(法政大学経営学部教授 木村純子)
【まもなく発売】季刊『社会運動』2025年4月発行【 458号】特集:食の自治の可能性を拓く 瀬戸際にある飼料とNON-GMO
テリトーリオとは
―まず、テリトーリオとは何か、ということをお話しいただけますか。
ひとまず「同じ経済的・文化的・社会的なアイデンティティを共有している都市と農村の集合体」と定義させていただきます。旧市街とそれを取り囲むようにひろがる田園で構成されるようなひとまとまりの地域のイメージです。日本の場合ですと、昔の藩のイメージが近いかもしれません。一国一城のお殿様がいて、経済的にも文化的にも自立している。廃藩置県があり、さらに市町村合併を繰り返して経済的・文化的・社会的なまとまりが壊れてしまったいまの日本の自治体からは、ちょっとイメージしにくいかもしれません。私は大阪出身ですが、北摂と呼ばれるエリアの出身なので、同じ大阪府でも南部の岸和田エリアとは文化が違うというアイデンティティがあります。なんとなくおわかりいただけますでしょうか。
テリトーリオは地理的境界だけに規定されるものでもありません。イタリアの場合、チーズやワインなどの産品は文化的・歴史的背景があるので、テリトーリオをシンボリックに表すことができます。例えばワインはその地域の在来品種のブドウを使って作られていますし、チーズについても、例えば水牛のモッツァレッラチーズの文化があるカンパニア州では、それをずっと守り続けているので、住民も含むテリトーリオの人びとのコミュニティが形成され、アイデンティティとなっています。イタリアの人たちは、日本の人たちとは比較にならないくらい、自分が住んでいる地域、郷土への愛着が強いということも強調しておきます。
私が調査をしたトスカーナ州の南部を例にすると、標高1738メートルのアミアータ山の東側の山麓は世界遺産に登録されているオルチア渓谷などの観光名所があり、かつての巡礼ルートのフランチジェナ街道だったり、シエナも近いので産業的に栄えていたのに対して、山の西麓は水銀鉱山が閉山されてからは経済的・文化的発展が遅れていました。逆に、それは生物多様性や、中山間地での農業活動に守られてきたゆえの固有の景観を維持することにつながりました。その結果、人口千人に満たないセッジャーノ村を中心に8つの自治体が9世紀から栽培してきた土着品種のオリーヴを搾って作るオイルを原産地呼称保護(PDO)に登録し、アミアータ西麓テリトーリオとして認知されるようになりました。
こうした例を見ると、物理的に最初からテリトーリオというものがあるわけではなく、人びとの内発的でボトムアップ型の活動プロセスそのものがテリトーリオを創出するといった方がいいかもしれません。イタリアはいま、このテリトーリオ戦略で農村の輝きを取り戻しているようです。
(抜粋)