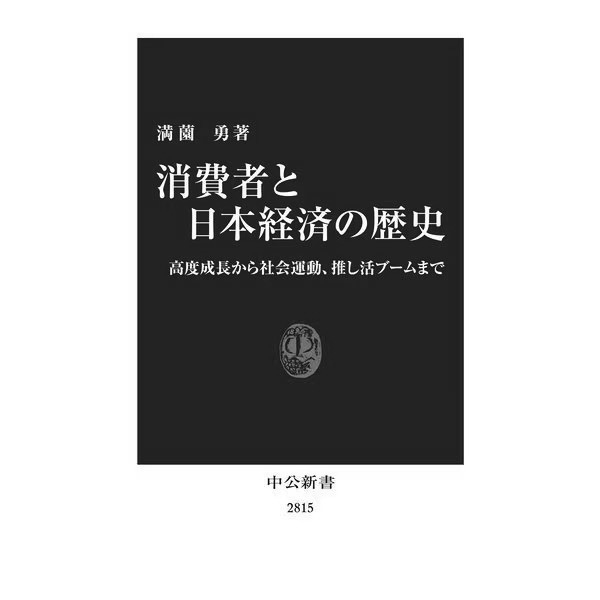書評①『消費者と日本経済の歴史』
【発売中】季刊『社会運動』2025年4月発行【 458号】特集:食の自治の可能性を拓く 瀬戸際にある飼料とNON-GMO
私らしい生活を求める時代の生協、生活クラブ
生活クラブ事業連合生活協同組合連合会 加工食品・生活文化部 部長 木下雅晴
1996年、新卒で生活クラブ・神奈川に入職。配送やコモンズ担当を経て、2007年より生活クラブ連合会で加工食品開発、システム開発、カタログ制作、消費委員会事務局を経て現職。
本書の帯に記載されている「買い物は社会を変えたのか」という問いに対し、生活クラブの共同購入運動に照らし合わせ、私は「買い物は社会を変えられた」と答えたい。
1945年(昭和20年)8月15日の終戦後、日本は農業を中心とした一次産業の占める割合が大幅に上昇した。「欲しがりません勝つまでは」の標語が示すように、戦争に資源を集中した影響により日本は食料が不足していたことから、国民の命をつなぐための食料生産が重視された。
しかし、1950年(昭和25年)には鉱工業生産が急速に回復・発展し、経済の正常化が進むと日本は1955年(昭和30年)から高度成長期に突入し、目覚ましい経済発展を遂げる。
本書では高度成長期以降の消費者と日本経済の歩みを、3つに分ける。
1960年代から1970年代前半までは、消費意欲が強く、大量生産・大量消費に象徴される商品の買い手としての「消費者の時代」とする。
1970年代半ばから1980年代半ばまでの、モノが充足され画一的な生活からの脱却、環境汚染問題による消費者の生活を見直し、「私らしい生活」といった生活様式の個性化を求める「生活者の時代」。
1980年代後半から2000年までの、個性化に対応したモノの価値に加え、無形物である顧客満足サービスを追求する「お客様の時代」。
このように3つの時代に分け、各時代で成功を収めた経営者の理念に照らしながら、消費者の視点から社会や経済の変化を具体的に解説している。
生活クラブが「生活者の時代」に
そのうち生活クラブは「生活者の時代」で取り上げられている。この時代は中内功氏率いるダイエーがバリュー主義(消費者が商品に求める価値を基準に売価が設定され、生産コストは無視される)を掲げ、「店頭で客と接する流通業者こそが価格決定権を握る必要がある」と強調し、スケールメリットを背景に徹底した安売りで発展を遂げていた。
これに対して生活クラブは、牛乳の共同購入を通じて、ただ購入するだけではなく生産側のコストを学び、自分たちが望む食品を中小メーカーと一緒に開発することで、スーパーでは手に入らない「消費材」を生み出した。「消費材」はスーパーの商品より高価であっても「生産コストや価値をわかって食べる」ことで適正価格による持続可能な生産と消費を実現した。
この対比から、生活クラブが資本主義に対するオルタナティブ(もう一つの選択肢)を創りあげ、買い物(共同購入)で社会を変える実践をしたことが再確認できる。
また、「生き方を変えよう」のスローガンのもと、生活クラブが合成洗剤による環境汚染問題に取り組み、せっけん運動や代理人運動を通じて社会を変えようとする「加害者にならない生き方の実践」も取り上げられている。
これらは、前述されている「生活者の時代(消費者が生活を見直し、私らしい生活様式を求める)」に見事に当てはまっており大変共感できる。
さらに本書では「消費者の時代」「生活者の時代」「お客様の時代」に加え、新たな時代の潮流として「エシカル消費」「応援消費」「推し活消費」を紹介している。成熟した社会において消費者がこれからの社会を変える可能性や責任についても言及しており大変興味深い。生活クラブ運動の存在意義や未来の社会を変える創造の一助になる一冊ではないだろうか。
(抜粋)