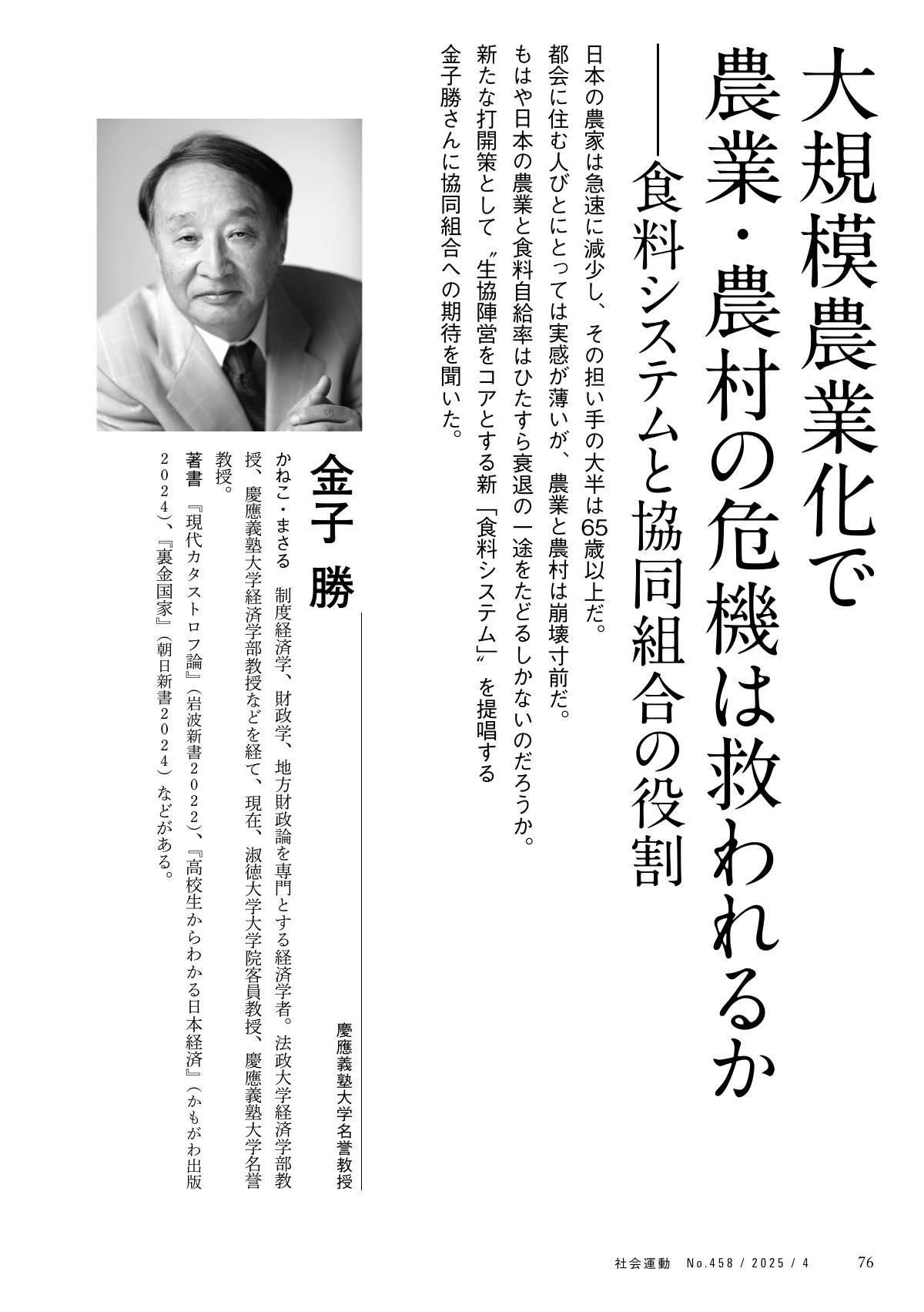●大規模農業化で農業・農村の危機は救われるか
(慶應義塾大学名誉教授 金子 勝)
【発売中】季刊『社会運動』2025年4月発行【 458号】特集:食の自治の可能性を拓く 瀬戸際にある飼料とNON-GMO
農業者と農村の人口減少が激しい
5年ごとに農林業センサスが公表される。2025年はその年に当たる。過去のデータを見るかぎり、農家数が急減し、中小零細農家の淘汰が進んでいる。図1を見ると、2005年に208万5千あった農業経営体数は、2020年には109万2千まで半減している。また図2が示すように、この5年間(2015~20年)をとっても、10ヘクタールを境にして中小零細農家の淘汰が進んでいる。2025年センサスもこの傾向は続くだろう。
こうした状況の下、2024年5月に食料・農業・農村基本法の見直しが行われた。1961年の農業基本法、1999年の食料・農業・農村基本法に続く基本法の改正である。ロシアのウクライナ侵略を契機にした食料情勢の変化に伴う食料安全保障上のリスクの高まりや、地球環境問題への対応が改正の理由とされている。
しかし、能登半島地震の復興状況に関する報道を見ているかぎり、現在の自公政権の下では農村の荒廃は止まらないことが懸念される。政府は地方を切り捨てているのではないか。そういう視点から見ると、今回の改正基本法には根本的な論理矛盾がはらまれている。この改正基本法でも、1961年の農業基本法以来、大規模化だけを念頭にした「成長型モデル」を前提にしており、大規模化による農業の生産性向上政策を進めれば進めるほど、先に見たように農家数がますます減少していくからである。
ところが、政府には農村が維持できなくなっているという危機感が欠如しており、農村の維持のために何をなすべきかという「攻めの論理」がまったく無い。衰退するままに任せていくという姿勢なのである。これでは、改正基本法は、かえって農業と農村の荒廃を進めてしまう「農村破壊法」になりかねない。
(抜粋)