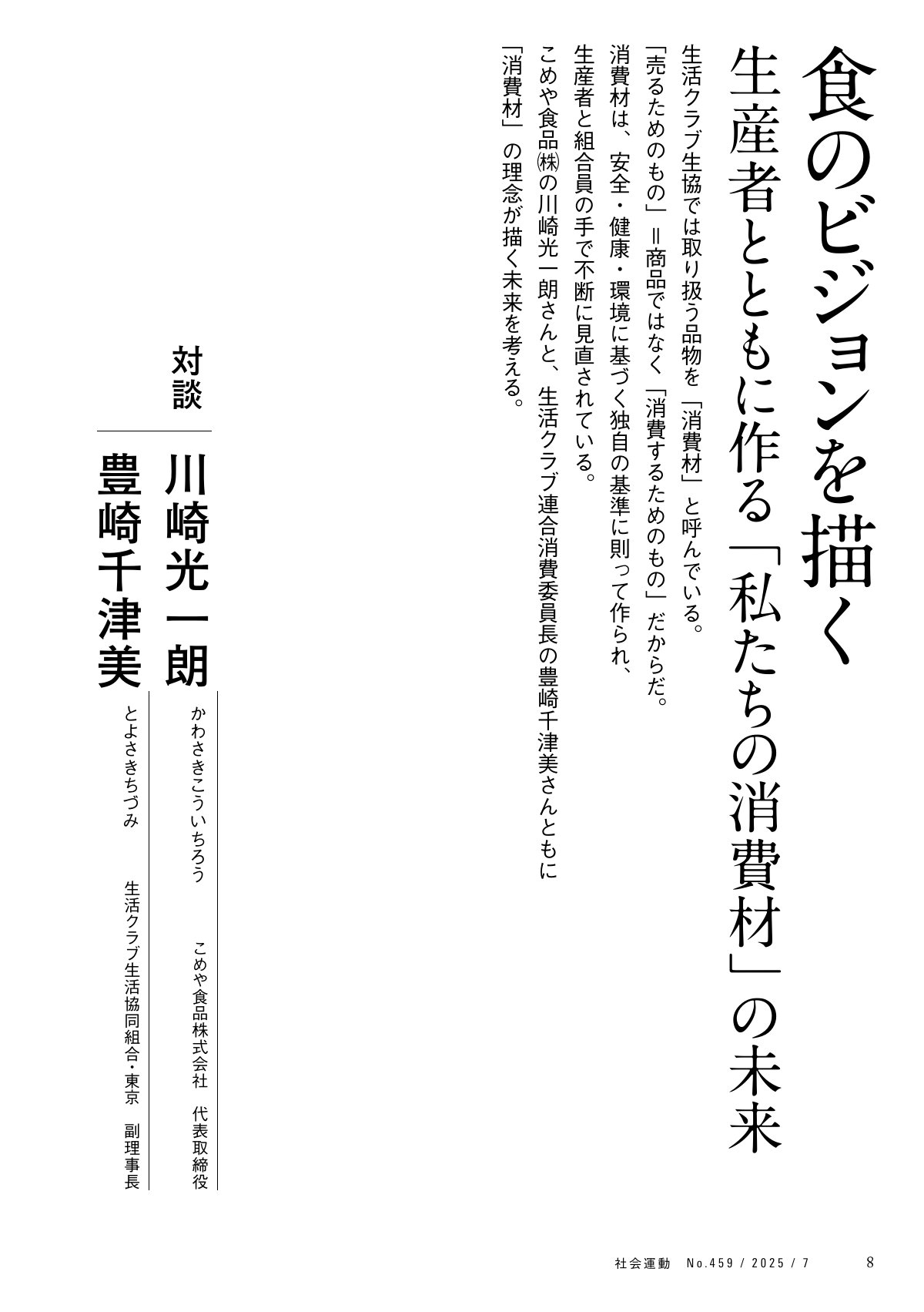●対談 食のビジョンを描く
こめや食品株式会社 代表取締役 川崎光一朗/生活クラブ生活協同組合·東京 副理事長 豊崎千津美
食べる人が生産現場を点検する活動
―「私たちの消費材」は、どのように継承されてきたのでしょうか。
豊崎 私の場合、理解を深める経験と場を与えられてきました。なかでも、一年をかけて一つのテーマに沿って学習会や交流会を企画する活動にかかわった経験が大きかったです。そのときのテーマは「食酢」で、まず市販品と消費材を比較して、参加した組合員と「味が違うね」「生活クラブの方がツンとしないね」などと感想を共有しました。その後、遺伝子組み換えについて問い合わせてみると、市販品のメーカーは「表示していなくても原料のアルコールに関しては分別せず使用しています」という回答。生活クラブの生産者からは「原料の原料まで遺伝子組み換えではないことを確認しています」という答えが返ってきました。
こうした学習や調査の後で、実際に生産現場を訪れて監査する持続可能な生産と消費推進制度「消費材StepUp点検(以下、ステップアップ点検)」に参加し、最後に生産者と交流会をしました。遺伝子組み換え原料を使っていないアルコールを探す並々ならぬ苦労話を工場長から直接聞いたり、昔ながらの木桶での醸成過程を見たり、ごみやCO2排出を削減するために洗びん機を導入して「Rびん(リユースびん)」を使っている現場を知って、「食べる責任」をより強く感じました。生産者と組合員が丹念に作り上げてきた消費材の価値を参加したメンバーみんなで共有できて、他の組合員にも積極的に伝えられるようになり、利用がすごく増えました。消費材のことを伝えれば共感が広がり、「私たちの消費材を使おう」という人が増える。それが私の原体験です。
初めてステップアップ点検に参加したときは「私みたいな素人が監査するの?」と頼りない気持ちになりましたが、やってみると、自分たちが「こうして欲しい」と伝えた希望が実現できているかを確認する活動で、よりよい消費材にしていくために生産者と一緒に点検するのが大事なのだと理解できました。
川崎 最近、当社でもステップアップ点検があって担当の組合員の監査を受け、報告会と交流会にも参加したのですが、これは本当に生活クラブらしい活動だと改めて感じました。組合員のみなさんは本当によく勉強してから足を運んでくれます。ステップアップ点検のプログラムが終わっても2〜3時間雑談します。そんなふうに時間をかけて、真剣に、一緒に考えてくれるのは、生産者としてはとてもうれしいことです。市販品だとバイヤーや市場の担当者が「こういうものが売れそうだ」という予測に沿って商品を作るので、消費者は生産者の苦労や「おいしく食べてもらいたい」という思いに触れずにパソコンでポチッと注文するだけになる。生活クラブの消費材の「使用価値」と一般市場の「顧客ニーズ」とは、似て非なるものなんですよね。
(抜粋)