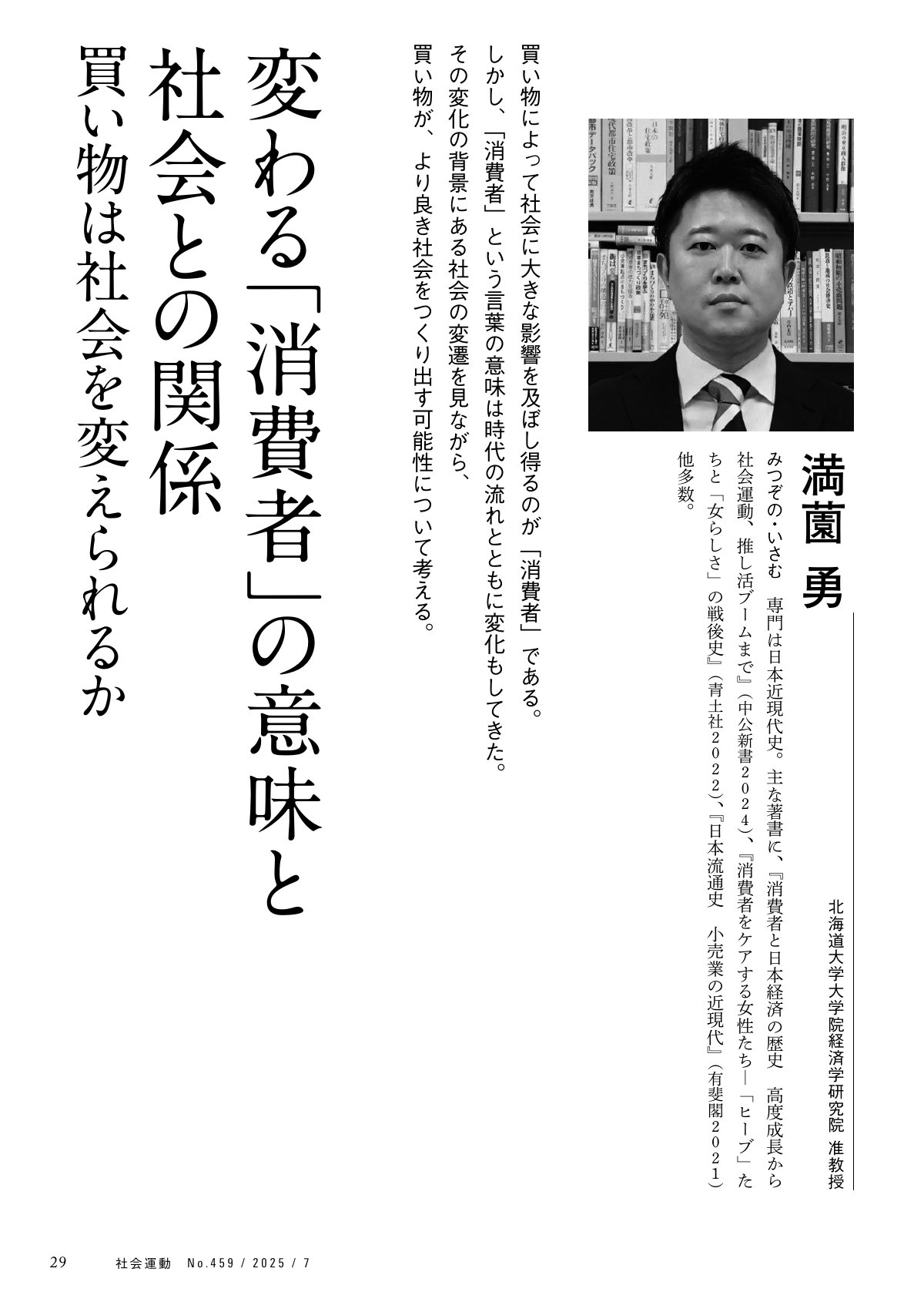●変わる「消費者」の意味と社会との関係
北海道大学大学院経済学研究院 准教授 満薗 勇
「消費者」の変遷を見る四つの観点
―「消費者」という言葉の変遷は、利益・権利・責任、そしてジェンダーの観点から見ていくと把握しやすいと著書『消費者と日本経済の歴史』(『社会運動』458号106ページ書評参照)に書かれています。解説していただけますか。
いま私たちは「消費者」という言葉を普通に使っていますが、実は一般の人たちに使われるようになったのは1960年代くらいからという、比較的新しい言葉です。当初は「事業者の利益」に相対するものとして「消費者の利益」を強調するような文脈で使われました。事業者側の都合で考えられたものが消費者の不利益をもたらす場合がある。それに対抗するために消費者の「利益」が強調されたわけです。
また「消費者の権利」は1960年代に米国のケネディ大統領が打ち出したもので、早くから日本にも紹介されていました。消費者は事業者に対して情報や経済力の格差、そして生身の人間であることなどから、構造的に弱者の立場にある。それを前提として、消費者の権利は保護されなければならないという観点で、日本の消費者運動の現場を中心に使われてきました。
一方、「消費者の責任」については、ややもすると権利と裏腹の関係と捉えられがちですが、そうではなくて、消費者には究極的には社会や経済を動かしていく責任があるという考え方です。一つひとつのモノを買うという行動が、生産のあり方や産業が環境に及ぼす影響などの原因になっているのだから、その立場を自覚して責任ある行動を取るべきだという観点になると思います。
これら消費者の利益・権利・責任という言葉は、それぞれ次元が異なる問題ではあるのですが、局面ごとに、無自覚に使い分けられたり、あるいは使い分けられなかったりしながら、一般の人たちにも浸透してきたという流れがあります。
そしてもう一つのジェンダーについてですが、消費者といえば、家族のケアを担い、その責任を負っている家庭の主婦がそれに該当する、その立場を代表するというような、社会的なジェンダー秩序の観点からの認識というものがあります。高度成長時代の日本では、消費者という言葉の担い手は主婦であると一般的に理解されていた面があるのです。これらの観点を意識しながら「消費者」という言葉の変遷を見ていくと、いろいろと見通しがよくなるというのが私の考えです。
(抜粋)