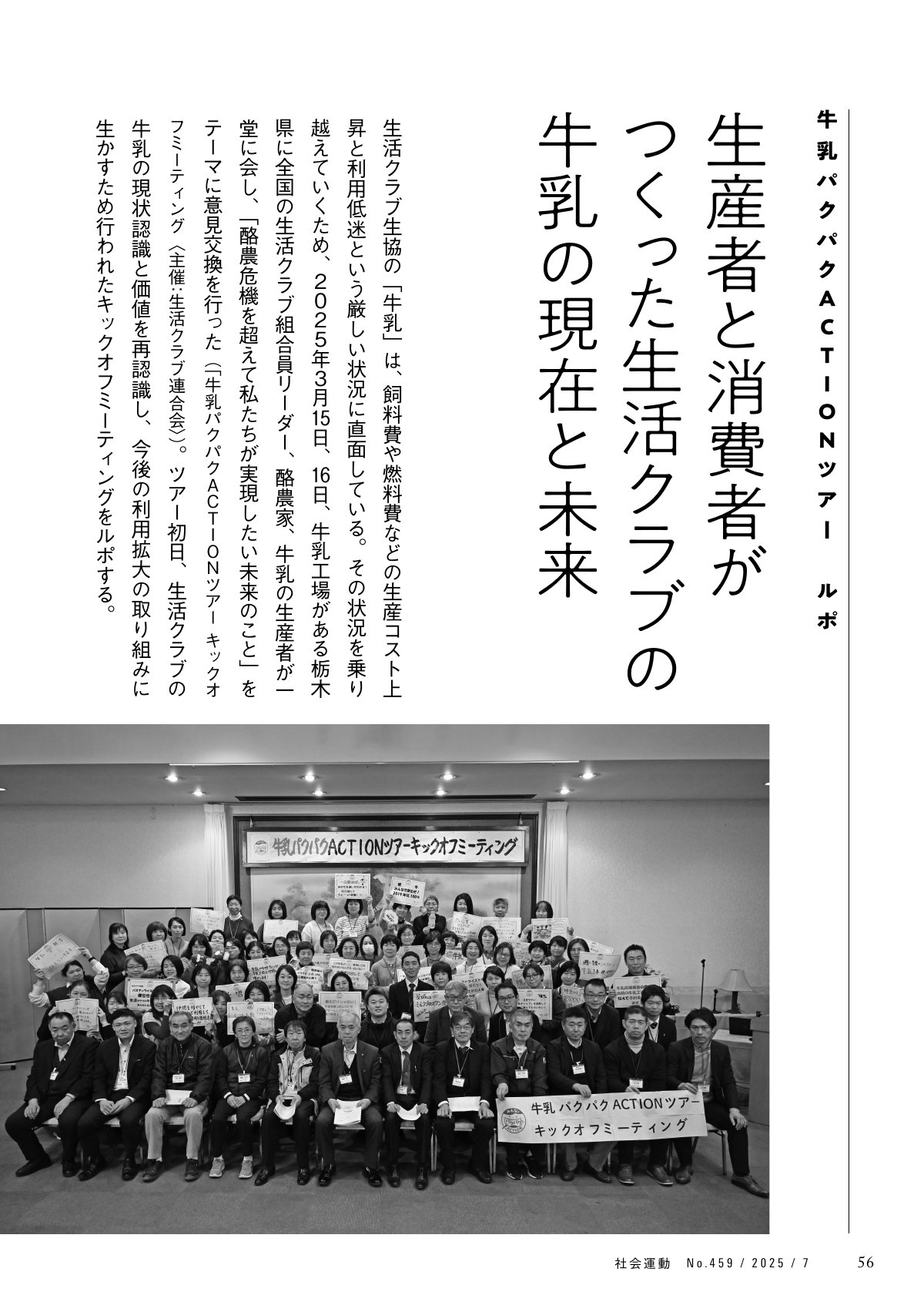●牛乳パクパクACTIONツアー ルポ
酪農危機を超えて私たちが実現したい未来のこと
開催にあたり、柳下信宏さん(生活クラブ連合会専務理事)は、参加者へ次のように挨拶した。
生活クラブの歴史は牛乳の歴史と言っても過言ではありません。1965年、東京都で「牛乳を安く飲むために生活クラブに入りましょう」と約200人の仲間を募り、牛乳の共同購入を始めました。それは、消費者が共同購入活動で大手乳業メーカー主導の価格設定に異議を申し立てる運動でもありました。そして、1968年10月に「生活クラブ生協」の創設。さらに本物の牛乳を求め、「素性確かなものを適正価格で」という、生活クラブの消費材開発の基本姿勢がつくられていきました。牛乳は生活クラブの運動に大きな影響を与え、活動を牽引してきた消費材です。
生活クラブの牛乳の生産者である新生酪農株式会社は、組合員と生産者が共同出資して作った自前の牛乳工場です。現在は、千葉県長生郡睦沢町・栃木県那須塩原市・長野県安曇野市の3カ所に工場があり、それぞれ周辺の指定酪農家の生乳を原料に生産しています。
近年の活動としては、飼料価格や燃料費の高騰などで経営状況が悪化した指定酪農家からの支援要請を受け、生活クラブは2023年2月から3月にかけて組合員に「酪農応援緊急カンパ(以下、カンパ)」を呼びかけました。集まったカンパ総額5348万1000円を、提携する酪農の生産者団体の那須箒根酪農業協同組合、農事組合法人新生酪農クラブ、南信酪農業協同組合に贈りました。さらに、継続的な支援をするために2023年4月から「牛乳応援基金」を開始(牛乳1品目2円の基金)し、酪農家を応援しています。
一方で、2001年から23年までの900ミリリットルびん牛乳実績推移(図1)が示すように、牛乳の消費量が年々下がっています。2014年には約1000万本の利用がありましたが、23年までに約30パーセント減少しています。
生産者も組合員もそれぞれに課題を抱え、生活クラブの牛乳は厳しい状況にあります。今回のキックオフミーティングは、生産者と組合員の意見交換で互いの相互理解を深め、牛乳を利用し続ける未来を描き、様々な取り組みを続けていく場にしていきたいと思います。
(抜粋)