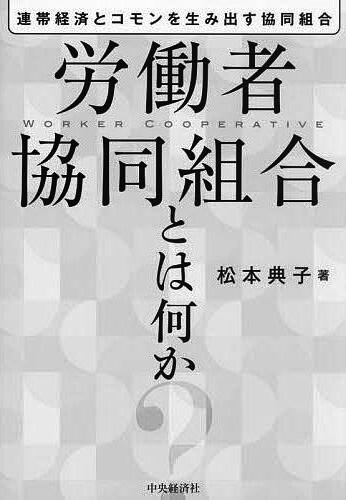書評①『労働者協同組合とは何か』 藤井恵里
2度目の国際協同組合年に『労働者協同組合とは何か』が出版された。
まだ耳慣れない、施行されて3年も経過していない新しい協同組合法を幅広く取り上げ、関心と可能性を促す本書が出版されたことは、ワーカーズ・コレクティブ(協同労働)運動を進めてきた私たちにとっては、この上なく嬉しい。
著者の松本典子さんは、労働者協同組合法施行後、既存の労働者協同組合のみならず、全国各地の新たな労働者協同組合に足を運び見聞を深め、ご自身も在住する磐田市で仲間と「労働者協同組合いわたツナガル居場所ネットワーク」を設立し活動している。
また、大学生の頃からワーカーズ・コレクティブの現場に触れ、博士論文の研究対象やNPO法人アビリティクラブたすけあいの理事として関わった経験、執筆にあたりたくさんの文献やヒアリングを通して、ワーカーズ・コレクティブや関連する生活クラブ運動のことを関心と愛情をもって、多くのページを割いて紹介していただいたことにまずは感謝申し上げたい。
そして、消費者であることに留まらず、生活者として自らが必要なモノやサービスを生み出す生産者となり、生活圏の中で働く場を創出し、生活者運動、市民運動、協同組合運動を展開してきたワーカーズ・コレクティブの社会的意義は小さくないと評価していただいた。
生活クラブとワーカーズ・コレクティブの関係
本書では労働者協同組合が「人間らしい生活と労働を取り戻し、ひいては人間力を回復させる」ことにどのような意義と役割を持ち得るのかという点を中軸に据えている。
他者に仕えて働くことや会社の利潤のための労働に疑問を持ち始めたり、地域や人を中心に据えた仕事へのやりがいに気づき始めた人が増えつつあり、協同組合に関心がなかった市民層からの労働者協同組合の設立も増えている。
そういった大きなポテンシャルがある一方で、労働者協同組合を協同組合の中でもっともマネジメントが難しい組織だとしているが、私はむしろ最もマネジメントしやすいのではと思う。
ワーカーズ・コレクティブの場合は、全員参加の総会、毎月の事業や運動推進にかかわる会議も原則全員参加で行うという、直接民主主義を原則としているからだ。その中で各々が主体として関わり合う関係性が醸成される。ともに働き合い、仕事もお金も喜びも困難もみんなで分け合い地域で生きる。これは、構想と実行を一致させる働きだからこその醍醐味であり「腑に落ちる働き方」と捉えたい。
ワーカーズ・コレクティブにそれができるのは、「自分で考え、自分で行動する」「自発性に基づく組合員主権」という生活クラブ運動の理念を基礎に発展してきたからだと思う。
文中にも労働者協同組合の働き方としてもよく使われる「構想と実行の一致」は、まさに「自分たちで考え、行動する」ことであり、労働者協同組合に限らない協同組合運営の在り方そのものなのではないかと本を読んでつくづく思った。
本書は、労働者協同組合を知りたい、学びたいという声に応え、広く優しく、時には深く研究者、実践者、生活者として多角的にとらえ、労働者協同組合、協同労働に興味を持ち始めた方々にもとても読みやすくまとめられている。
特にワーカーズ・コレクティブ運動を含む生活クラブ運動に携わる組合員、職員の皆さんには、ぜひ手に取って読んでいただきたい1冊です。
労働者協同組合を入り口として、ワーカーズ・コレクティブに関心をもってくださる人がこの本によって増えることを願って。
(全文)