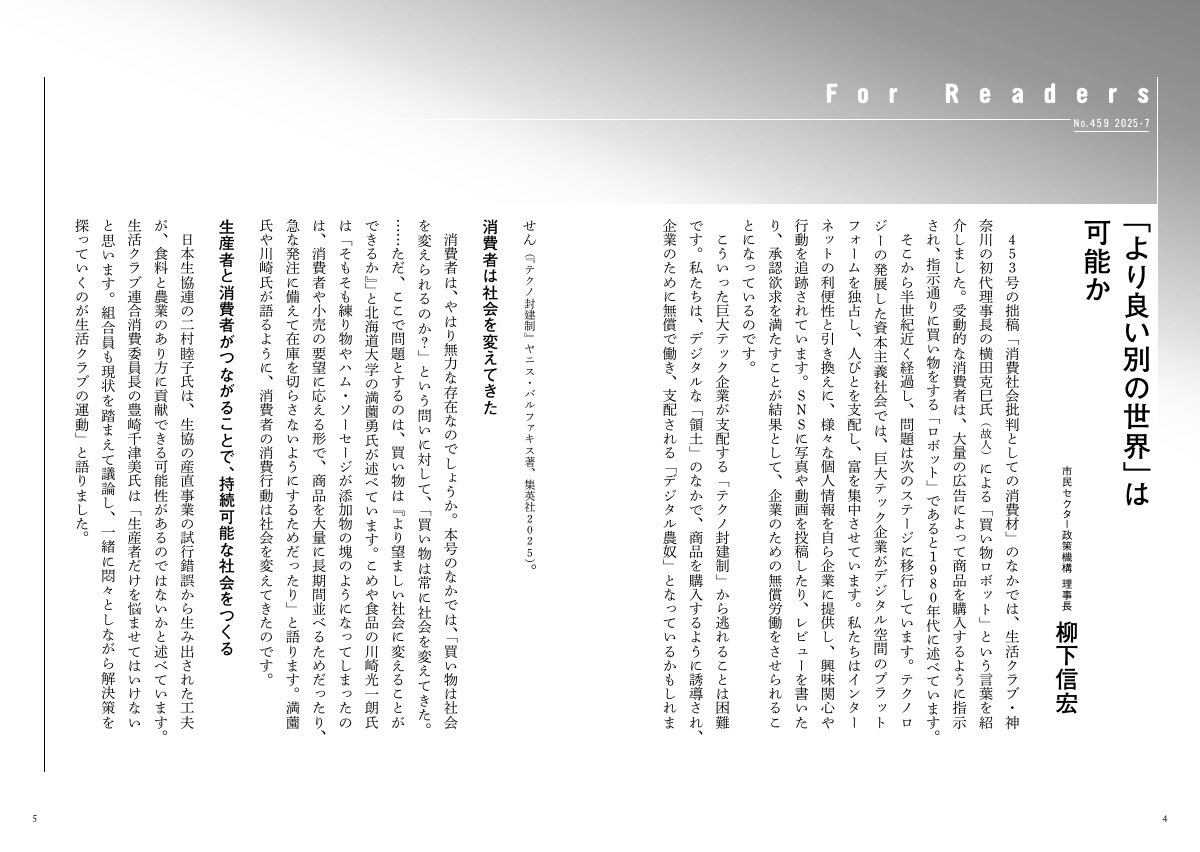「より良い別の世界」は可能か
市民セクター政策機構 理事長 柳下信宏
453号の拙稿「消費社会批判としての消費材」のなかでは、生活クラブ・神奈川の初代理事長の横田克巳氏(故人)による「買い物ロボット」という言葉を紹介しました。受動的な消費者は、大量の広告によって商品を購入するように指示され、指示通りに買い物をする「ロボット」であると1980年代に述べています。
そこから半世紀近く経過し、問題は次のステージに移行しています。テクノロジーの発展した資本主義社会では、巨大テック企業がデジタル空間のプラットフォームを独占し、人びとを支配し、富を集中させています。私たちはインターネットの利便性と引き換えに、様々な個人情報を自ら企業に提供し、興味関心や行動を追跡されています。SNSに写真や動画を投稿したり、レビューを書いたり、承認欲求を満たすことが結果として、企業のための無償労働をさせられることになっているのです。
こういった巨大テック企業が支配する「テクノ封建制」から逃れることは困難です。私たちは、デジタルな「領土」のなかで、商品を購入するように誘導され、企業のために無償で働き、支配される「デジタル農奴」となっているかもしれません(『テクノ封建制』ヤニス・バルファキス著、集英社2025)。
消費者は社会を変えてきた
消費者は、やはり無力な存在なのでしょうか。本号のなかでは、「買い物は社会を変えられるのか?」という問いに対して、「買い物は常に社会を変えてきた。……ただ、ここで問題とするのは、買い物は『より望ましい社会に変えることができるか』」と北海道大学の満薗勇氏が述べています。こめや食品の川崎光一朗氏は「そもそも練り物やハム・ソーセージが添加物の塊のようになってしまったのは、消費者や小売の要望に応える形で、商品を大量に長期間並べるためだったり、急な発注に備えて在庫を切らさないようにするためだったり」と語ります。満薗氏や川崎氏が語るように、消費者の消費行動は社会を変えてきたのです。
生産者と消費者がつながることで、持続可能な社会をつくる
日本生協連の二村睦子氏は、生協の産直事業の試行錯誤から生み出された工夫が、食料と農業のあり方に貢献できる可能性があるのではないかと述べています。生活クラブ連合消費委員長の豊崎千津美氏は「生産者だけを悩ませてはいけないと思います。組合員も現状を踏まえて議論し、一緒に悶々としながら解決策を探っていくのが生活クラブの運動」と語りました。
本号のなかでは、生活クラブの「共同開発米」「牛乳」「鶏肉」「トマトケチャップ」をめぐる、「より望ましい社会」に向けた、生産者と消費者の具体的な実践が述べられています。生産者だけ、消費者だけで何かが実現できたわけではありません。これらの記事のなかからは、生産者と消費者がつながることの可能性を知ることができると思います。
「より良い別の世界」を想像する
朱寧悳氏と崔珉竟氏の講演録は、生活クラブと韓国協同組合の交流について学ぶ非常に貴重な記録です。人びとの熱い思いが国境を越えて協同組合を広げ、協同組合が実現可能な代替案であることを証明してきたことがわかります。
「協同組合運動の中心的な目的は、より良い別の世界を創ること」(レイドロー報告)です。消費者の組織である生協(消費生活協同組合)の組合員が、社会の仕組みと自らの消費のあり方を見つめ直し、「買い物ロボット」や「デジタル農奴」を抜け出す途を模索することは、「より良い別の世界を創る」ことにつながるはずです。
本号の各記事が、皆さんの議論の素材となり、実践につながることを期待しています。
(全文)