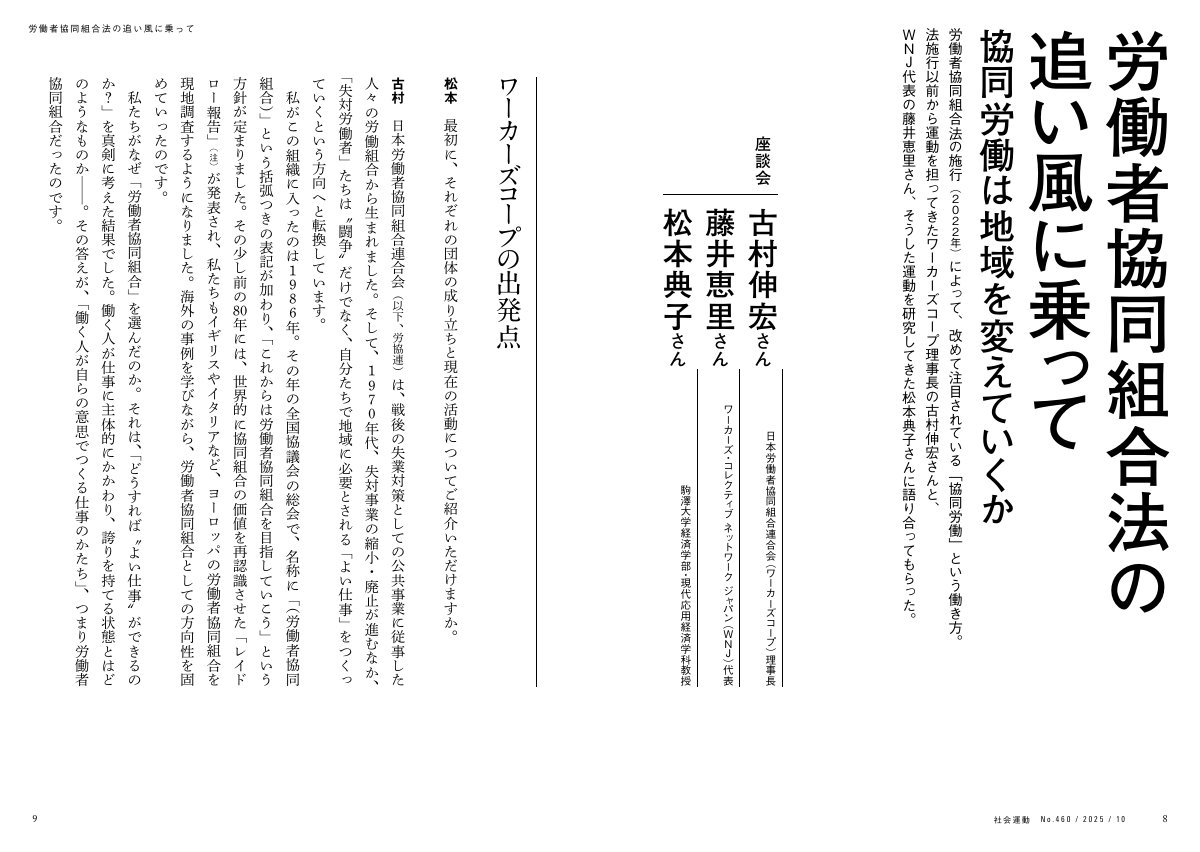●労働者協同組合法の追い風に乗って
日本労働者協同組合連合会(ワーカーズコープ)理事長 古村伸宏/ワーカーズ・コレクティブ ネットワーク ジャパン(WNJ)代表 藤井恵里/駒澤大学経済学部・現代応用経済学科教授 松本典子
多様なローカルの価値を生み出す「経営」と「経済」
松本 ところで「社会的連帯経済」という言葉。ワーカーズコープではあまり使われていないような気がしますが、いかがですか?
古村 原則には入っていますが、確かにあまり使っていないかも。違う言い方をしているかも知れません。ワーカーズ・コレクティブでは、使っているのかな。
藤井 そうですね。確かに「私たちは社会的連帯経済の一翼を担っている」と全国会議などで掲げると、共感してもらえます。現場では日々の業務に追われ、その意識が薄れがちなのが現実ですが、この考え方は大事にし続けたいと思っています。私たちがなぜ地域で事業を起こすのか。その原点を見失っては、活動の意味が曖昧になってしまいますから。
ワーカーズ・コレクティブは、地域性や立ち上がりの背景もそれぞれ異なり、多様なスタイルで活動していますから、一律に意識を揃えるのは難しい。でも、私はむしろそこに価値があると思っています。地域ごとに異なる個性を持つ存在が全国に広がっていること自体が、すでに社会的連帯経済の一つのかたちなのだと。
これまでの日本社会は、地域の多様性よりも効率や画一性を重視してきました。でも最近は、ローカルの力を活かす動きも行政のなかに少しずつ生まれてきています。そんな時代に、「社会的連帯経済」という言葉が“ひとつの枠組み”のように響いてしまうとしたら、少し注意が必要かもしれませんね。
古村 私たちワーカーズコープでは、「どんな経済を目指すか」という抽象的な議論よりも、「自分たちの経営とは何か」をずっと問い続けてきました。「労働者が企業の主人公になる」という理念から「全組合員経営」という実践へ。さらに「共感の経営」「社会連帯経営」と、時代に応じて言葉は変化しましたが、私はむしろ、原点に立ち返る必要を感じています。
つまり、「どんな地域や社会をつくりたいのか」というビジョンなしに経営を語っても、閉ざされた企業経営と変わりません。お金の出入りを管理するだけでは、社会的連帯経済の実感にはつながらないのです。
だからこそ、「社会的連帯経済」という言葉を借りるだけでなく、自分たちの現場から湧き出るローカルな言葉で、自分たちの目指す経営から経済を語ることが大事なのではないかと思っています。
(抜粋)