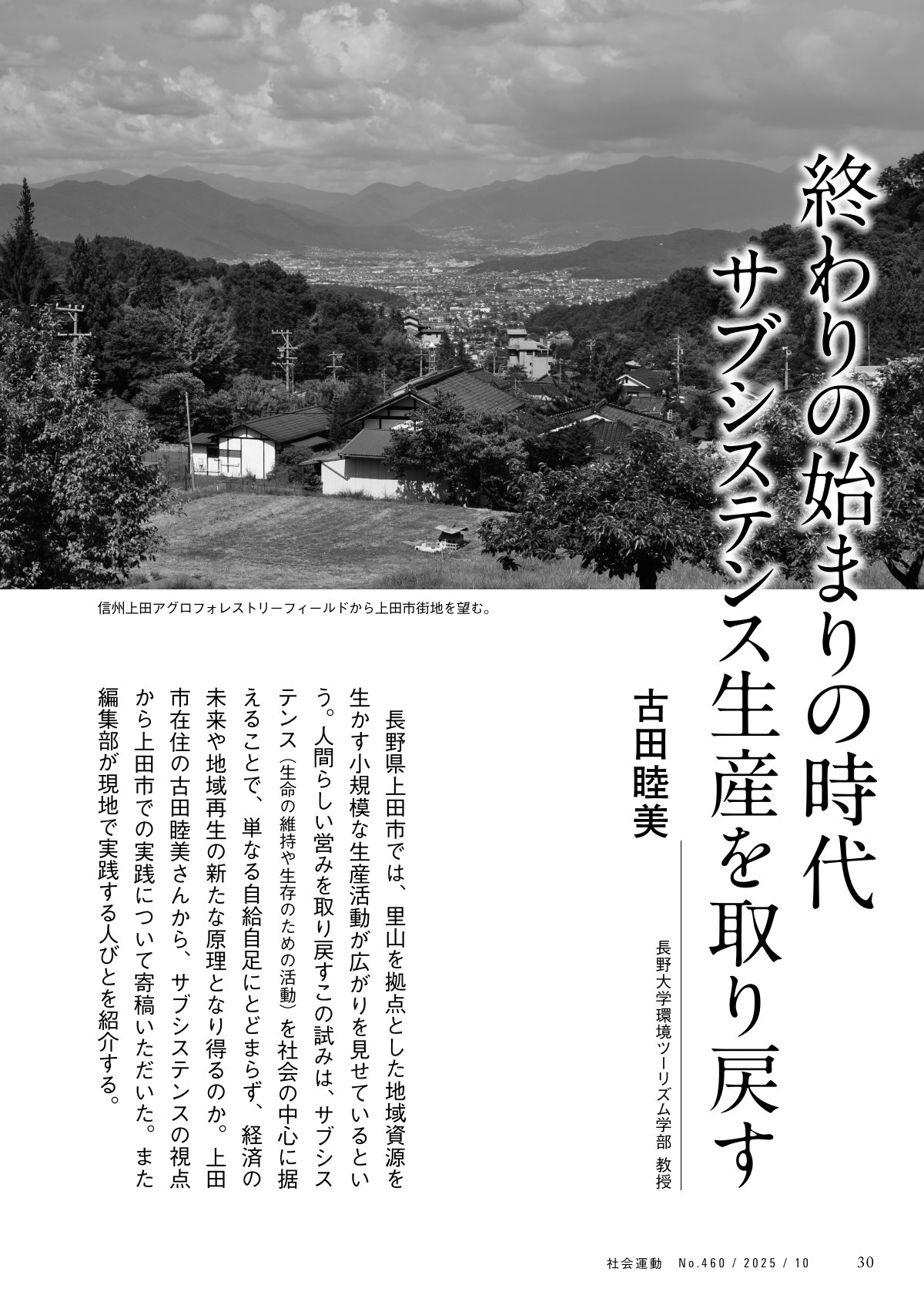●終わりの始まりの時代 サブシステンス生産を取り戻す
長野大学環境ツーリズム学部 教授 古田睦美
この数年で、第二次世界大戦後から長きにわたり続いてきた国際秩序は大きな変化を余儀なくされている。単一のルールに基づいた市場のグローバリゼーションが世界を席巻し生活世界をも植民地化してきた。個人所有、私有化といった画一的で個性のない何か「普遍的」な近代的価値を普及させるイデオロギーが台頭し、ローカルな風土に適応した文化、人のつながりと共有の感覚、自然と共生してきた知恵や技をことごとく破壊してきた時代であった。この時代の終焉の始まりは、断末魔とも見える凶暴化をともなっており手放しで喜ぶことはできない。しかし、確かな変化が多くの人の眼前に現れている。とくに、貨幣、株、金融、利子、通貨、電子マネー、そのようなカネの流れをめぐる状況の変化は富者にとって安泰であった体制を揺るがす時代となっている。
カール・ポランニー(ウィーン出身の経済人類学者。1886-1964)が言うように、歴史上、社会は経済の成立基盤であり、経済に社会が支配されているような現在の体制は特異なのである。
社会運動にとって、長いスパンでみれば、市場が支配する時代にあっては、カネを支配する者、購買力を持つ者はそれなりの力をも持つのであり、その時代にあって消費者運動もまた対抗力を持ち得た。金があればなんでも買える高度大衆消費社会が、社会発展の目的とされた時代には、消費者が何かを買うときに、どのような作り方のどのような商品を買うのかということは、それを作り流通させている組織や仕組みに一票を投じているようなものであり、それは一種の権力行使なのであった。
これまでの単一の市場の支配が変化している。消費者運動のあり方も変化する必要があるだろう。ではこの大転換の先のビジョンをどう描けば良いのだろうか。
(抜粋)