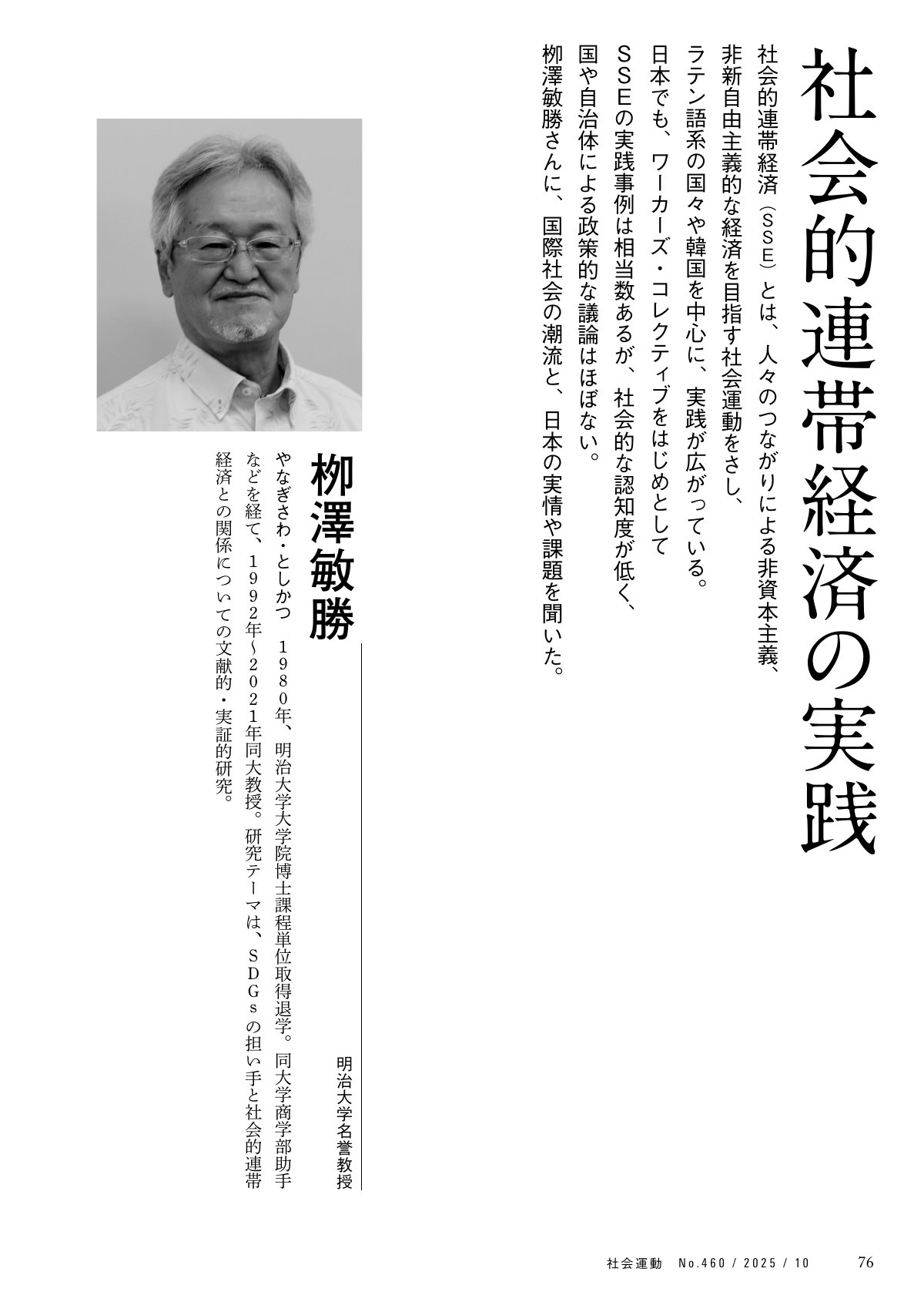●社会的連帯経済の実践
明治大学名誉教授 栁澤敏勝
資本主義社会で生じた諸問題に対抗する
―そもそも社会的連帯経済とは何でしょうか。
社会的連帯経済(以降、SSE)とは、「社会的経済」と「連帯経済」が合体したものです。社会的経済をもっとも簡潔に定義しているのが1983年のフランスの「社会的経済法」です。それによると、協同組合と共済組合とアソシエーション(非営利、NPO)の三つを社会的経済としています。
では、連帯経済とは何か。数多くの草の根自助グループによって維持される社会のありようをいいます。背景には1980年代に新自由主義的な経済が展開し始めて格差が拡大したなかで、従来の社会的経済では対応しきれない事態が起こります。そのためイタリアで「社会的連帯協同組合」という助け合いの仕組みがつくられ、ヨーロッパ各地でも様々な取り組みが盛んに見られるようになりました。それらが連帯経済と呼ばれています。日本では子ども食堂やフードバンクなどが相当します。
19世紀に生まれた人々の助け合いの仕組みとしての社会的経済と、1980年代以降、やむにやまれずみんなが集まってなんとかしようとつくった連帯経済、この二つが合体したものが社会的連帯経済です。どちらも、困っている人たちが資本主義社会のなかでなんとかしようとしているのは同じなので、一緒にやるべきだという議論が2010年代半ばに出てきたのです。
SSEの国際的な議論を集約しているのが、2013年に発足した国連SSEタスクフォース(TFSSE)です。正式メンバーは18の国連機関と経済協力開発機構(OECD)、そして世界銀行です。オブザーバーとして国際協同組合同盟(ICA)はじめ14のNGOが参加しています(2024年)。TFSSEでは「社会的連帯経済」を世界の共通語にしようということが言われるようになりました。加えてSSEの中核は協同組合であると位置づけたTFSSEの議論をふまえれば、協同組合陣営の役割は重要なのです。
先ほどのSSEの図式に当てはめると、生活クラブは協同組合、つまり社会的経済です。これに対して、個々の組合員がいろいろな思いでつくってきたワーカーズ・コレクティブは連帯経済そのものです。生活クラブが人、物、金、情報などの資源を使って、小さな協同組織であるワーカーズ・コレクティブをサポートする関係をうまくつくっていけば、そこで社会的連帯経済が生まれることになります。
(抜粋)