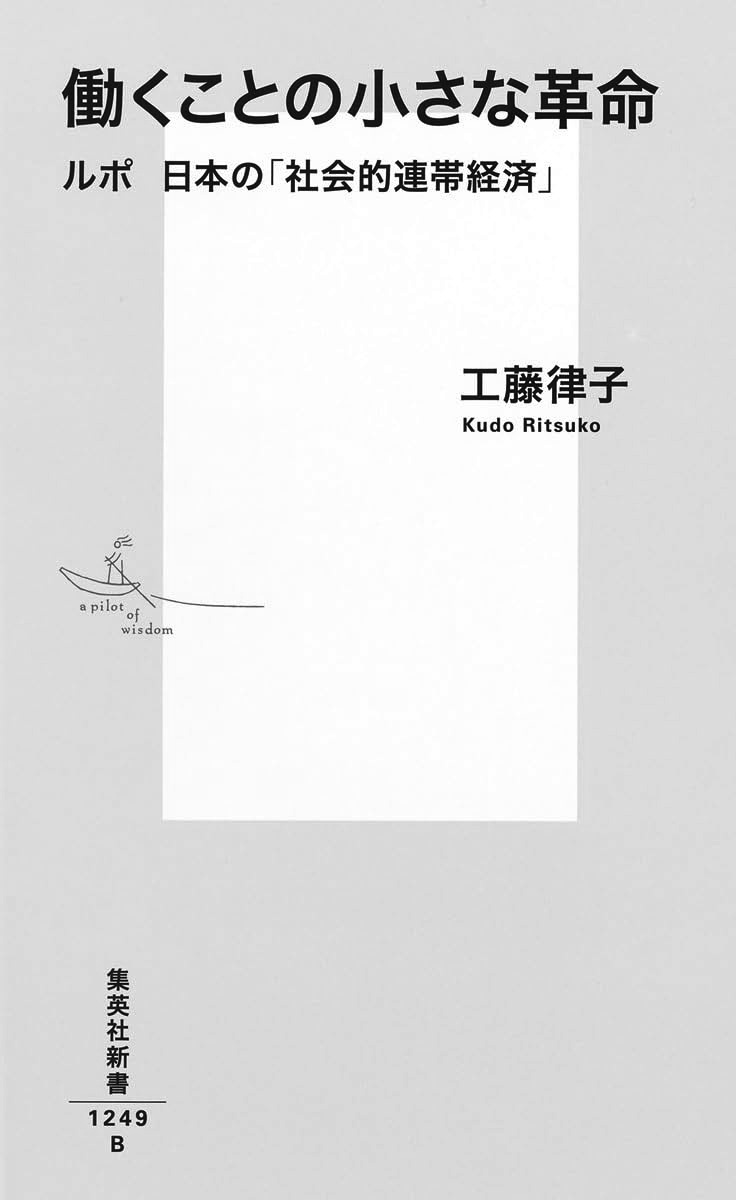書評①『働くことの小さな革命』 植田敬子
本書は日本での社会的連帯経済の多くの事例を詳しく紹介している。社会的連帯経済とはその名のとおり、誰をも見捨てることなく社会を良くする目的のもとに、みんなが参加してつながる経済のことである。
かつて経済制度は資本主義対社会主義という枠組みで考えられた。今や、その両方ともうまくいかないことに多くの人が気づいている。社会主義は中央集権型経済を実践するために独裁権力を産み出し国民の自由を奪った。資本主義には複数の型があると言われているが、日本に大きな影響力をもつアメリカ型では、格差が拡大し過ぎて深刻な分断が生じ内戦勃発の可能性まで指摘されている。アメリカからの影響を強く受ける日本でも格差は拡大傾向であり、それをくい止めるためにはアメリカ型資本主義にとって代わる経済モデルが必要である。
社会的連帯経済の担い手がとても魅力的な人たちなのだ
資本主義経済に代わるべきものとしてヨーロッパ、特にスペインで注目されているのが社会的連帯経済である。社会主義経済が中央集権型であるのと真逆で、社会的連帯経済の意思決定はボトムアップ型であり、参加者はみんな対等である。このことから社会的連帯経済は民主主義との親和性がきわめて高いことがわかる。民主主義が世界中で危機に瀕している現在、社会的連帯経済の重要性は増すばかりである。
このような重要性にもかかわらず、社会での認知度は低い。特に日本では言葉も概念もあまり浸透していない。そのために実際には社会的連帯経済を実践しているにもかかわらず、それと認識していない当事者が多いと著者は指摘する。著者は日本各地から社会的連帯経済の実践例を集めているが、その担い手達全員が魅力的な人達であることに驚かされる。分野は介護・福祉、子育て、映像制作、便利屋、弁当販売、小売業、居場所づくり、飲食店、食品販売、金融、有機農業、フードバンク、宿泊所、子ども食堂、八百屋、フェアトレード、再生可能エネルギー発電所、高齢者住宅、カフェ、等々多岐にわたる。
そこで働く人達が全員魅力的で幸福感に満ちていることには明確な理由がある。第一に、自分の利益のために働いている人は一人もいない。少しでも人や社会の役に立ちたいという熱い思いで働いている。その対象が自分の身近で困っている人達のこともあれば、将来世代や外国の人達のこともある。その熱い思いが達成できた時、あるいは目標に一歩でも近づけたとき彼ら彼女たちは幸せである。金銭的報酬は多くなくてもそれを償ってあまりある充実感・達成感・幸福感・連帯感を得ている。
第二に、働き方が既存の民間企業とは異なる。上司の命令に従って働くのではなく、参加者一人ひとりの意思が平等に尊重される協同労働を行う。労働の内容が上司の命令によって決まるのではなく、自分達は何をしたいのか、どんな方法でするのかを話し合いによって決める。参加者の工夫や創造性が発揮される。参加者は対等に協同労働するのであるから、民間企業での昇進競争や人間関係に悩まされることはない。むしろ信頼できる仲間に恵まれる幸せを感じることができる。
社会的連帯経済は小さな地域コミュニティでの経済活動が出発点である。さまざまな経済活動がつながり連帯することによって多くの人を巻き込み、最終的には誰一人として取り残されることのない社会を作ることができるはずである。これは楽天的過ぎる予測に見えるかもしれないが、本書を読むと実現できるという希望と勇気が湧いてくる。
(全文)