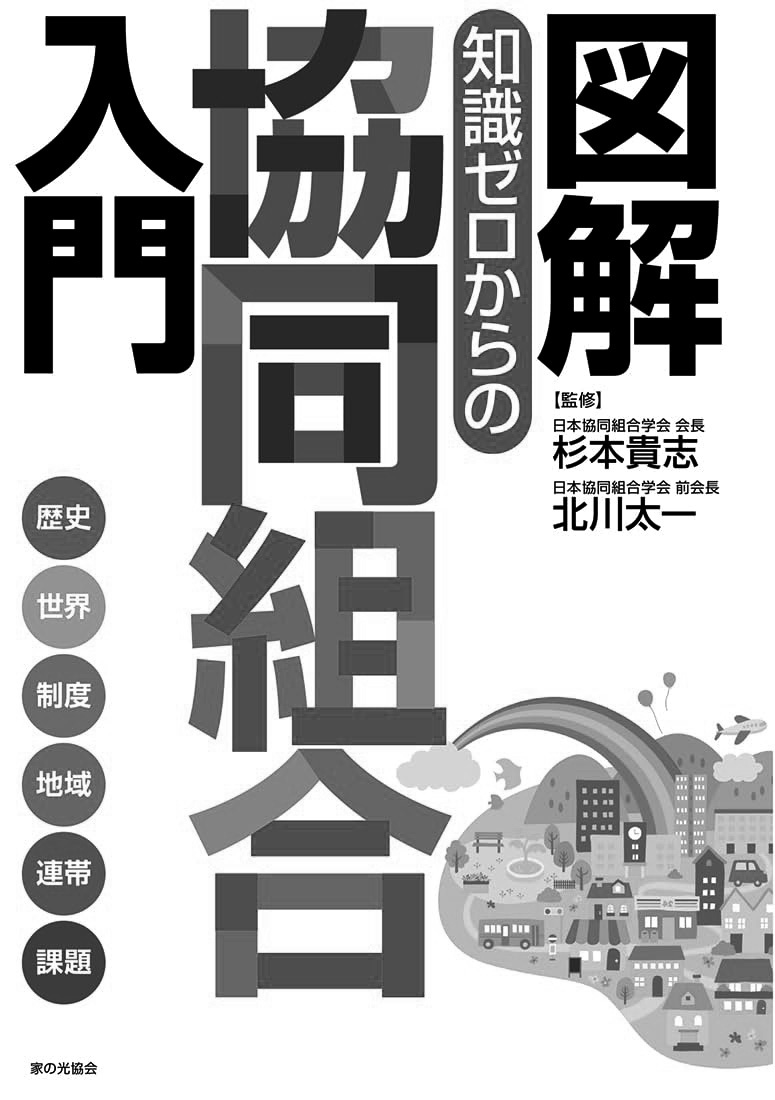書評②『図解 知識ゼロからの協同組合入門』 室田元美
入門と書かれた上に、「知識ゼロから」とのダメ押しまであり、国際協同組合年である今年、多くの人に読んで知ってほしいとの願いが伝わる本である。書籍紹介を担当する筆者自身、「ロッチデールって、誰?」というほど知識ゼロなのだが、そんな者にもとてもわかりやすく、読み物として一気に引き込まれていく内容になっている。
協同組合はどう生まれ、どんな変遷を遂げてきたか。農協や漁協、生協のみならずどんな職種の人びとが協同組合を作ってきたか。世界でいま、協同組合の理念やしくみが必要とされているのはなぜか。一度通読したあとは、興味のある章を選んで読むのもいい。
まず始まりは、産業革命と生みだされた格差。農村地主たちの平均寿命が50歳前後であったのに対し、マンチェスターやリバプールの労働者は10代後半だったという。1820年代に思想家や運動家が「競争」ではなく「協同」を打ち出し協同組合がいくつも作られたものの、継続しない。1844年にようやく英国ロッチデール(地名でした!)の人びとが「小麦粉、砂糖、バター、オートミール」の4品目で成功を収め、そこから協同組合運動は世界に広がっていった。
日本には文明開化期に伝えられた。しかし明治以降の富国強兵、植民地支配に協同組合も取り込まれていく。大正デモクラシーの頃には、賀川豊彦が市民主体の消費組合を立ち上げた一時代もあったが、戦争に突入すると日本政府が占領地に作った協同組合で現地経済を管理するなど、アジア侵略に加担した。戦後、日本の生活協同組合が「平和とよりよい生活のために」を掲げるのは、戦前戦中の苦い経験と反省があったからだという。
戦後は第一次産業、医療、教育、文化、芸能やスポーツなどでも協同組合が誕生した。1970〜80年代には、生協の発展が家庭にも大きな影響をもたらした。一般企業は出資者、経営者、顧客が別々の人格であるのに対し、協同組合は組合員が自ら出資し、自ら経営し、自ら利用する「三位一体性」で成り立っており、組合員が持つ権利は「一人一票」、全員が平等である点が大きく違う。協同組合のガバナンスの基本が「組合員民主主義」であることを、改めて実感できる。
生協がつくる参加型民主主義と課題
日本の協同組合の歴史は合併の歴史、と本書には記述されている。生協を例にとると1960〜70年代に物価高や食の安全への関心の高まりから各地で新設され、組合員は「班」を単位として共同購入や運営に参加した。その後は地域で合併し、90年代以降には組合員数の増加にもかかわらず生協数は減ってきている。さらに大規模合併により、組合員との距離が拡大したことや参加意識の後退などが指摘されている。
協同組合らしさを取り戻すために、本書で推奨されているのが、東京と神奈川の生活クラブ生協で行われている分割・分権化だ。「小さな協同」を作り出し、必要に応じて他の協同組合や地域組織とつながることが、課題解決のカギになりうるとのことである。
グローバル経済の進展による弊害が顕著になっている現在、国際労働機関(ILO)は協同組合には「危機の時期におけるビジネスモデルの強さ」が存在すると評価しているという。SDGsの担い手としても注目される。資本や権力を集中させない第三の選択としての協同組合の役割は、今後ますます大きくなるだろう。
(全文)