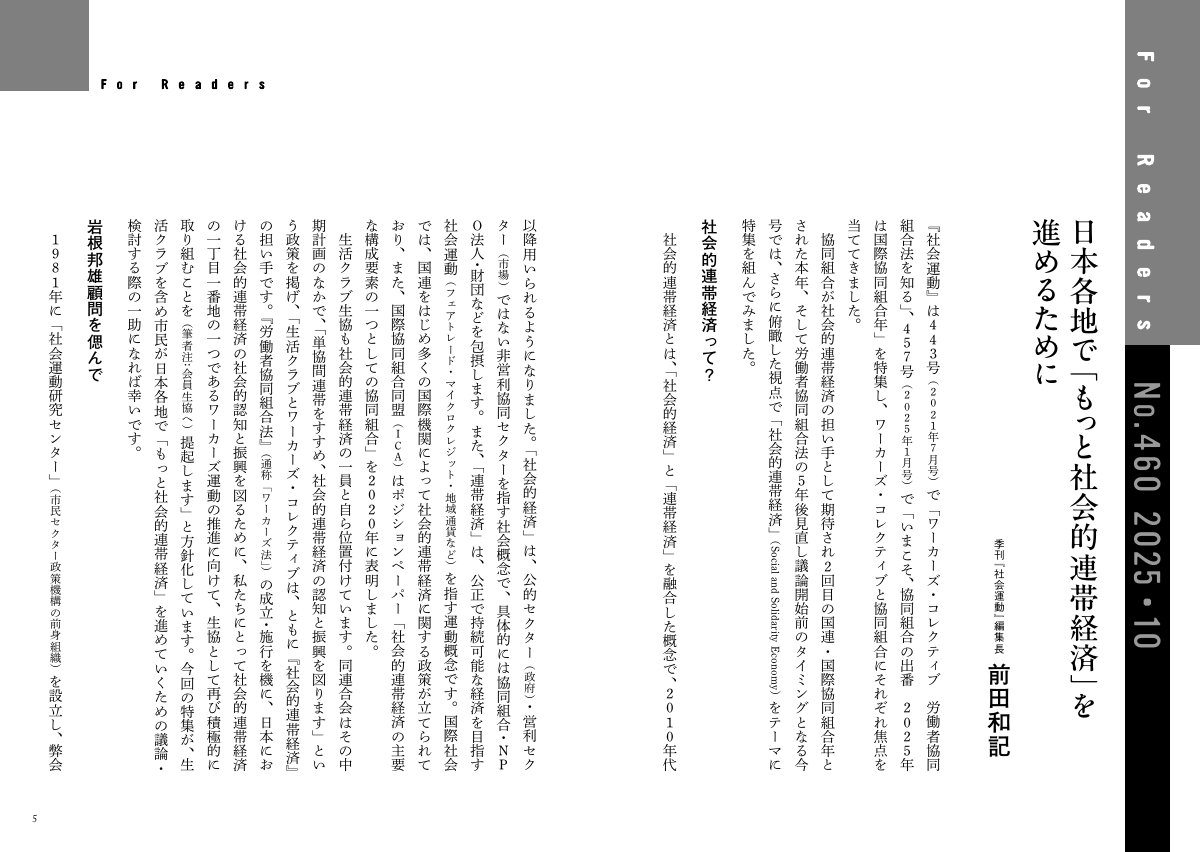日本各地で「もっと社会的連帯経済」を進めるために
季刊『社会運動』編集長 前田和記
『社会運動』は443号(2021年7月号)で「ワーカーズ・コレクティブ 労働者協同組合法を知る」、457号(2025年1月号)で「いまこそ、協同組合の出番 2025年は国際協同組合年」を特集し、ワーカーズ・コレクティブと協同 組合にそれぞれ焦点を当ててきました。
協同組合が社会的連帯経済の担い手として期待され2回目の国連・国際協同組合年とされた本年、そして労働者協同組合法の5年後見直し議論開始前のタイミングとなる今号では、さらに俯瞰した視点で「社会的連帯経済」(Social and Solidarity Economy)をテーマに特集を組んでみました。
社会的連帯経済って?
社会的連帯経済とは、「社会的経済」と「連帯経済」を融合した概念で、2010年代以降用いられるようになりました。「社会的経済」は、公的セクター(政府)・営利セクター(市場)ではない非営利協同セクターを指す社会概念で、具体 的には協同組合・NPO法人・財団などを包摂します。また、「連帯経済」は、公正で持続可能な経済を目指す社会運動(フェアトレード・マイクロクレジット・地域通貨など)を指す運動概念です。国際社会では、国連をはじめ多くの国際機関によって社会的連帯経済に関する政策が立てられており、また、国際協同組合同盟(ICA)はポジションペーパー「社会的連帯経済の主要な構成要素の一つとしての協同組合」を2020年に表明しました。
生活クラブ生協も社会的連帯経済の一員と自ら位置付けています。同連合会はその中期計画のなかで、「単協間連帯をすすめ、社会的連帯経済の認知と振興を図ります」という政策を掲げ、「生活クラブとワーカーズ・コレクティブは、ともに『社 会的連帯経済』の担い手です。『労働者協同組合法』(通称「ワーカーズ法」)の成立・施行を機に、日本における社会的連帯経済の社会的認知と振興を図るために、私たちにとって社会的連帯経済の一丁目一番地の一つであるワーカーズ運動の推進に向けて、生協として再び積極的に取り組むことを(筆者注:会員生協へ)提起します」と方針化しています。今回の特集が、生活クラブを含め市民が日本各地で「もっと社会的連帯経済」を進めていくための議論・検討する際の一助になれば幸いです。
岩根邦雄顧問を偲んで
1981年に「社会運動研究センター」(市民セクター政策機構の前身組織)を設立し、弊会の顧問を永らく勤めてくださった岩根邦雄さんが、2024年12月に永眠されました。故人を偲び、特集の一つに「追悼 岩根邦雄」を設けました。 岩根さんと旧知の友人だった写真家・桑原史成さんが、追悼文を寄せてくださいました。桑原さんは『社会運動』8号(1980年11月号、社会運動研究センター準備会発行)から表紙の写真を、そして350号(2009年5月号)からは巻頭グラビアを提供してくださった方です。
紙面に限りがあり、お話を伺うべき多くの方々に取材できなかったことが心残りです。今号には載せられませんでしたが、何らかの形でお話を伺う機会をと考えています。
(全文)