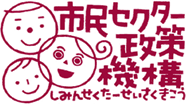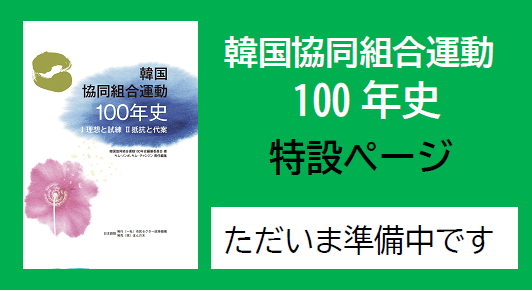第5章 日帝下の労働運動・農民運動と社会主義協同組合
イ・ギョンナン
1.社会主義民族解放運動の転換と協同組合運動の変化
1920年代後半には、労働運動や農民運動などの民衆運動が成長したことにより、民族解放運動の様相も大きく変化した。こうした民族解放運動は、資本主義や社会主義、社会民主主義などのイデオロギー、あるいは天道教〔<歴史の窓1>の訳注1参照〕やキリスト教〔韓国語で「キリスト教(기독교)」は一般的にプロテスタントを指す〕といった宗教上の信念に基づく新国家建設の方針に従って組織的に分化し、政策を具体化していった。そして、全国あるいは京城〔現在のソウル〕を中心とする運動から郡レベルの地域運動へと組織の軸足を移したことで、各地で青年運動、労働運動、農民運動、女性運動、新幹会〔朝鮮内のすべての政治勢力がかかわって結成した朝鮮独立運動組織。1927~31年〕支部などの運動が定着していった。そしてこれらの組織は、朝鮮青年会連合会や朝鮮労働総同盟、朝鮮農民総同盟、新幹会といった全国的な連帯組織を通じて結びついていた。さらに最も重要な変化は、労働運動と農民運動における主体形成が進んだことだった。農民運動にとっては、日帝〔日本帝国主義〕が政策的に進めた地主制や、不公平で商業的な農業と流通構造という、農民共通の問題を解決する必要があった。各地で農民は具体的な問題をめぐって議論し、組織的に闘争する事例が増えた。知識人を中心とする運動から、知識人と労働大衆とが団結をして取り組む運動に転換したといえる。
このように民族解放運動が変化するなかで、協同組合運動も同様に1920年代後半から系列化が鮮明になった。とりわけ社会主義に基づく協同組合論は、労働者・農民の運動と結びつくことによって活動も具体化した。地域における労働者・農民の組織化が一定の水準に達した地域では、消費組合運動も成長していったのである。
本稿では、日帝下における民族解放運動の主体が変化していったなかで、自主的な生活と闘争を通して消費組合としての特徴を持った協同組合運動がどのように展開したのか、またその運動論はいかなるものだったのかを振り返る。特に1920年代後半以降に広がった各地の労働運動・農民運動に注目する。運動の主体となった当事者たちは、自分たちの生活をどの方向に改革するのかを自ら決定して運動に飛び込んでいったからである。彼らの主張はきわめて広範囲で、労働者や農民に有利な政策を決定すること、様々な組織と協力して主体的に活動すること、それを実現するための社会改革の方向性、さらにはそうした価値観を共有する国際的な連帯にも及んだ。また、元山全域でのストライキを先導した元山労働連合会や、咸鏡南道の革命的農民組合は、地域のなかに労働者と農民が強力に組織されれば状況を大きく変えられるという事実を示した。それでも、こうした運動は日帝による厳しい弾圧を受けたため、地域のなかで長続きすることはできなかった。
この時、各々の主体がどのように動き対応したのか、その基礎にあった論理とはどのようなものだったかという点は非常に重要である。その論理によって、協力する勢力や達成目標、ビジョンと方向性が決まるからである。当時、社会主義運動の影響下にあった労働運動・農民運動の論理は、民族革命運動の階級性を強調する1928年の「12月テーゼ」や1930年の「プロフィンテルン〔赤色労働組合インターナショナル〕9月テーゼ」など、国際共産主義運動と朝鮮政策の転換に深く関連していた。そして運動の方向性は「大衆の中へ」ということであった。ちょうどこの時期に朝鮮の労働運動・農民運動が地域で組織化を始めたのである。こうして、社会主義系の民族解放運動家たちは労働者や農民の現場に運動の基盤を置く民族解放運動を開始した。こうした運動方針の転換のなかで登場した「階級的協同組合論」の内容についても考察することが重要である。
革命的労働運動・農民運動は、デモや集会、ストライキという形で登場した。それと同時に、彼らは水面下でも教育活動を行い、会って討論し、意思を共有して共に行動して、組織化を進めた。夜学を立ち上げて運営したり、大会を開催して集中すべき課題を確認して、勢力を拡大したのである。その一方、住民の日常的な要求に対応するため、消費組合を運営して安定した生活が実現できることを経験させた。このように協同組合運動は、労働者や農民の生活を支えながら、労働運動や農民運動と結びついていた。ただし、協同組合運動が順調に進むか否かは、内部における運営の力量と、外部からの支援の仕組み、そして日帝による抑圧政策体制によって左右されることになった。
(続きは本書をお買い求めください)